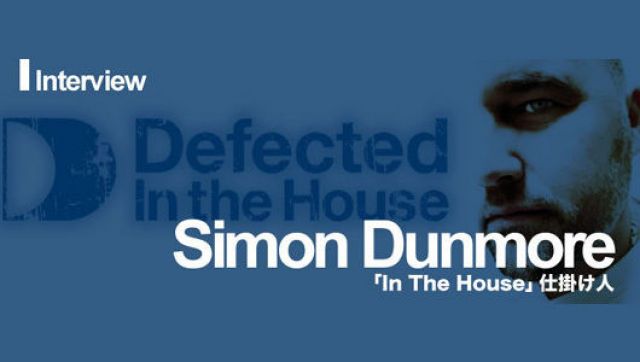そうですね。前作の「to come...」を、アランがA&Rだったフランスのイエロープロダクションズでリリースし、反応もよかったんです。だから次は制作から一緒にやろうという話になり、具体的に話も進んでいたんですが、途中、諸事情からアランと一緒にやる以前に、新作の制作自体が暗礁に乗り上げてしまって。その後、アランとも話をして、再開するんですが、一度、下がったモチベーションを上げるのはなかなか難しかったです。
そうですね。デモ制作に始まり、ヴォーカルなどゲストを決めて、レコーディング…と通常ならば、およそ3ヶ月くらいで集中してやるのに、なんだかんだでデモ作りを終えるだけで、結局、3年もかかってしまいました。
焦りは相当、感じましたよ。途中、パリコレの音楽をやったり、ベスト盤を出すなどして、気分を変えてみたり、自分の頭を整理するなどしたんですけど、そういうことをやればやるほど、かえってみんなから新作はいつだって言われる(苦笑)。あまりに訊かれるものだから、誰とも会いたくない時期もありました。
いつも最初に具体的には考えないほうなんですが、今回は今までのポエツの世界観から一歩抜け出て、より多くの人を惹き付けるものが作りたいと思いました。それからこれは今回に限らずこれからもずっとテーマになるかもしれませんが、時代に関係ない「いい曲」を作れたらなと思っていました。
ある時、曲名もわからないですが、たまたま50年代か60年代のポップスが流れていて、それがものすごく完璧な音楽に聴こえたんですよ。シンプルで無駄がなくて、それでいて心に染み入って感情を揺さぶるような。いい曲って時代を超越してるんですよね。頭をひねって変ったことや新しいことばかり考えるより、シンプルで人を惹き付けるタイムレスな「いい曲」を作らなきゃって思ったんです。
それともう一つ。ここ数年の新しい音楽に対して、興味が薄らいできたのもあるのかもしれませんね。それは自分の中で、たまたまなのかもしれませんけど、以前ならアンテナを張って、CDやレコードを買いまくっていたのが、今はまるでそんなことはなくなった。どうしても欲しいと思える作品が少ないんです。仕事の必要上から新譜を買うことはありますが、それ以外で買うことは随分減りました。デモ制作中にとにかくよく聴いていたのは古いレゲエ。あとはニューウェイブ、パンク。そういうものを聴きながら、これまで自分が作ってきたものが、現在も未来にも聴けるものなのか。そんなことを考えましたね。

まず何よりも大きいのはアランとの共同プロデュースってことと、「to come...」の後、メンバーが脱けて独りになったので、これまで二人で分担してやっていた作業をすべて僕自身がやるようになったことですね。今回は作曲からプログラミングから、基本的にすべてを一人でやっています。最初は、誰かに参加してもらうことも考えましたが、やっているうち、今回は自分一人でできるところまでやろうと思いました。ゲスト・ミュージシャンはエバートン・ネルソンとショーン・リーの二人だけですね。
エバートンとは、前作『to come...』で、すごく納得のいくものを作ることができたので次もまた彼と、よりスケールアップした形でやりたいと思っていたんです。
ヴォーカリストは最初、三人くらいにするつもりだったんです。作り手としてやりがいがあるし、聴く側にしても複数のヴォーカリストとの組み合わせを楽しむ人もいるだろうし。ところが、途中、アランから一人にしたほうがいいと言ってきました。いろんなヴォーカリストを入れると、サイレント・ポエツというイメージが散漫になってしまうから、一人に絞り込んだほうがいいんじゃないかと。あまり賛成ではなかったんですが最終的には納得しました。
実はすでにあるヴォーカリストでやることが決まっていたんです。でも、スケジュールの都合からギリギリのところで流れてしまった。そこで人選について再度、アランと相談したらショーンの名前を出してきたんですよ。ただ、僕自身はちょっと悩んだんです。彼の作品は素晴らしいけど当初の自分のイメージとは違う。そもそも彼のことを考えたことなんて一度もなかったんですからね。それをアランに伝えようとしたんですが、待てよ、と。合わないと思うからこそ、むしろいいんじゃないか、何より今回は今までと違うことをやろうとしてるんだから、と思ったんです。そう考え出したら、今度はむしろとてもいい人選のような気がしてきたんで、彼に決めました。アランは、あまりにスムースに、僕が了解したんで、意外そうだったけど。
前作でもそうだったんですが、デモテープを渡しただけです。そこに基本的なコードやメロを入れてあるので、それをベースにやってくれと頼みました。彼の場合、イメージと違うものをあげてくることはありませんし。
スタジオのブッキングからキャスティングまで、みなエバートンがやってくれました。レコーディングも調整する部分はありましたが、基本的には問題なく進みましたね。大満足です。
とりたてて意識していたわけではないですが、わからないではないですね。これまでのアルバムでは自分の感情をストレートに表現するのはどちらかといえば抑えてきたんです。ちょっと斜に構えてた部分もあったかもしれません。でも、いまはむしろ逆で、自分が生活する中で、感動したり、泣いたりするのは普通のこと。クサいって言われてもいい、むしろそういう気持ちを表に出したいって思ってましたから。それが自然と曲に現れるのかもしれませんね。
彼にも具体的には何も言っていないです。プロですから曲を聴けば自分が何をすべきかわかるはずです。デモを渡して、やりたいようにやってくれと。一ヶ月もしないうちに3曲が届きました。早かったですね。
すごく感動しました。それでいてキャッチーで覚えやすい、「いい曲」になったと思います。ショーンのほうも十分、満足していますね。
彼とは何度かデモ曲を渡して、さまざまなキャスティングのことから、いろいろ相談しつつやってきました。とにかく、今回は過去のポエツは卒業して次のステップに行くんだと何度も言われましたね。そんな彼の期待に応えなければと、常に思っていましたから気持ちの面でも励みになりました。レコーディングでは細かいところを補ってくれて様々なアイデアを出してきました。実際、アランのアイデアで曲がよくなることも多く、その都度、さすがだなと思いましたね。彼と組んだ事でサイレント・ポエツの違う魅力みたいなものが出たと思います。
前半はアランのスタジオで彼と編集作業をして、後半はパリ郊外にあるスタジオ、STUDIO DAVOUTに入って、アランは加わらずに、エンジニアのパスカルと作業しました。特にその後半のミックス・ダウンは本当にキツかったです。
パリでの作業には日本人スタッフが一人もいなかったことと、そもそもアルバム一枚すべてのミックスを海外でやるのは初めての経験でしたから。エンジニアのパスカルとももちろん初対面でそのペースに慣れるのがとにかく大変で。スケジュールもタイトでしたから休む間もほとんど無くストレスもたまるし、正直、逃げ出したかったです。過去に経験したレコーディング、特に日本でのレコーディングとは違いましたからね。
まあスケジュールやエンジニアにもよるんでしょうけど、スタジオに入る時間からして違いました。日本だとお昼から徐々にって感じですが、パリでは朝9時にはキッカリ、スタートしてました(笑)。終わりも早くてダラダラ深夜までやらないんです。それと一つ一つの作業に対し、その場で即、シロかクロかを決めないといけない。「とりあえず保留」ってのはなくて、とにかくすべてをどんどん明確にしながら進めて行く直感勝負なんですよ。基本的にはあれこれ悩んで後戻りしたりできませんでした。日本だと「なんか違うな」とか言って何度も何度も聴いたり1時間くらいお茶して考えたり、エンジニアにいろいろやってもらって、じゃあやっぱり最初に戻ろうかなんてやりとりがあったり、「う~ん、今日はもういいか。わかんなくなってきたから明日にしよう」なんてこともありますね(笑)。

まぁ、一概にはどちらがいいとも言えないですが、その場その場で即判断しなきゃいけないのは相当にキツかったですね。毎日、朝から晩まで気が抜けない。延々とやってるから、精神的にすり減った感じしました。しかもスケジュールが決まっていて、毎日、予定通りに完成させないといけないから、そのプレッシャーもあったし。心身の疲れから、ホテルに戻った途端、毎日、バタン!って、倒れ込むように寝てしまっていましたよ。
近いかもしれません。でも、判断が早いから、音がとにかくハッキリしているんです。考えながらやると、どっちのつかずの音になっちゃうことが多いですからね。最初は強い印象にした音も、悩んだ末、抑えて普通にしたりとか。
そうですね。作品的にも非常に納得のいくものができました。特にショーンとエバートンとコラボレートした二曲(「Man On The Street」と「Dumb Girl」)は完璧ですよ。もうあれ以上は何もしようがないですから。
もちろん「to come...」など、これまでにもある程度の満足感を得るものはありましたが、完成度ではこの二曲にはかないません。アルバム全体を通せば、もちろん、粗も見えるし後悔もありますが、それでも一つ一つ、決して何となくというレベルで作ったわけじゃないので、ものすごく自分の中では納得しています。それとやっぱり、パリのスタジオでああいう作業をしたということは、今までとは違いよりヨーロッパの音楽の現場を肌で味わった気がして、それもよかったですね。
そうですね。新しいサイレント・ポエツは始まったばかりですから。いずれにせよ、今回は一人になってゼロから始めて、時間がかかったけど何とかやり遂げた。みんなとコラボレートできたし、パリでの作業もプラスになった。それで最終的に納得できるものが出来上がったのは自分にとって自信になりましたね。
 まず何よりも大きいのはアランとの共同プロデュースってことと、「to come...」の後、メンバーが脱けて独りになったので、これまで二人で分担してやっていた作業をすべて僕自身がやるようになったことですね。今回は作曲からプログラミングから、基本的にすべてを一人でやっています。最初は、誰かに参加してもらうことも考えましたが、やっているうち、今回は自分一人でできるところまでやろうと思いました。ゲスト・ミュージシャンはエバートン・ネルソンとショーン・リーの二人だけですね。
エバートンとは、前作『to come...』で、すごく納得のいくものを作ることができたので次もまた彼と、よりスケールアップした形でやりたいと思っていたんです。
ヴォーカリストは最初、三人くらいにするつもりだったんです。作り手としてやりがいがあるし、聴く側にしても複数のヴォーカリストとの組み合わせを楽しむ人もいるだろうし。ところが、途中、アランから一人にしたほうがいいと言ってきました。いろんなヴォーカリストを入れると、サイレント・ポエツというイメージが散漫になってしまうから、一人に絞り込んだほうがいいんじゃないかと。あまり賛成ではなかったんですが最終的には納得しました。
実はすでにあるヴォーカリストでやることが決まっていたんです。でも、スケジュールの都合からギリギリのところで流れてしまった。そこで人選について再度、アランと相談したらショーンの名前を出してきたんですよ。ただ、僕自身はちょっと悩んだんです。彼の作品は素晴らしいけど当初の自分のイメージとは違う。そもそも彼のことを考えたことなんて一度もなかったんですからね。それをアランに伝えようとしたんですが、待てよ、と。合わないと思うからこそ、むしろいいんじゃないか、何より今回は今までと違うことをやろうとしてるんだから、と思ったんです。そう考え出したら、今度はむしろとてもいい人選のような気がしてきたんで、彼に決めました。アランは、あまりにスムースに、僕が了解したんで、意外そうだったけど。
前作でもそうだったんですが、デモテープを渡しただけです。そこに基本的なコードやメロを入れてあるので、それをベースにやってくれと頼みました。彼の場合、イメージと違うものをあげてくることはありませんし。
スタジオのブッキングからキャスティングまで、みなエバートンがやってくれました。レコーディングも調整する部分はありましたが、基本的には問題なく進みましたね。大満足です。
とりたてて意識していたわけではないですが、わからないではないですね。これまでのアルバムでは自分の感情をストレートに表現するのはどちらかといえば抑えてきたんです。ちょっと斜に構えてた部分もあったかもしれません。でも、いまはむしろ逆で、自分が生活する中で、感動したり、泣いたりするのは普通のこと。クサいって言われてもいい、むしろそういう気持ちを表に出したいって思ってましたから。それが自然と曲に現れるのかもしれませんね。
彼にも具体的には何も言っていないです。プロですから曲を聴けば自分が何をすべきかわかるはずです。デモを渡して、やりたいようにやってくれと。一ヶ月もしないうちに3曲が届きました。早かったですね。
すごく感動しました。それでいてキャッチーで覚えやすい、「いい曲」になったと思います。ショーンのほうも十分、満足していますね。
彼とは何度かデモ曲を渡して、さまざまなキャスティングのことから、いろいろ相談しつつやってきました。とにかく、今回は過去のポエツは卒業して次のステップに行くんだと何度も言われましたね。そんな彼の期待に応えなければと、常に思っていましたから気持ちの面でも励みになりました。レコーディングでは細かいところを補ってくれて様々なアイデアを出してきました。実際、アランのアイデアで曲がよくなることも多く、その都度、さすがだなと思いましたね。彼と組んだ事でサイレント・ポエツの違う魅力みたいなものが出たと思います。
前半はアランのスタジオで彼と編集作業をして、後半はパリ郊外にあるスタジオ、STUDIO DAVOUTに入って、アランは加わらずに、エンジニアのパスカルと作業しました。特にその後半のミックス・ダウンは本当にキツかったです。
パリでの作業には日本人スタッフが一人もいなかったことと、そもそもアルバム一枚すべてのミックスを海外でやるのは初めての経験でしたから。エンジニアのパスカルとももちろん初対面でそのペースに慣れるのがとにかく大変で。スケジュールもタイトでしたから休む間もほとんど無くストレスもたまるし、正直、逃げ出したかったです。過去に経験したレコーディング、特に日本でのレコーディングとは違いましたからね。
まあスケジュールやエンジニアにもよるんでしょうけど、スタジオに入る時間からして違いました。日本だとお昼から徐々にって感じですが、パリでは朝9時にはキッカリ、スタートしてました(笑)。終わりも早くてダラダラ深夜までやらないんです。それと一つ一つの作業に対し、その場で即、シロかクロかを決めないといけない。「とりあえず保留」ってのはなくて、とにかくすべてをどんどん明確にしながら進めて行く直感勝負なんですよ。基本的にはあれこれ悩んで後戻りしたりできませんでした。日本だと「なんか違うな」とか言って何度も何度も聴いたり1時間くらいお茶して考えたり、エンジニアにいろいろやってもらって、じゃあやっぱり最初に戻ろうかなんてやりとりがあったり、「う~ん、今日はもういいか。わかんなくなってきたから明日にしよう」なんてこともありますね(笑)。
まず何よりも大きいのはアランとの共同プロデュースってことと、「to come...」の後、メンバーが脱けて独りになったので、これまで二人で分担してやっていた作業をすべて僕自身がやるようになったことですね。今回は作曲からプログラミングから、基本的にすべてを一人でやっています。最初は、誰かに参加してもらうことも考えましたが、やっているうち、今回は自分一人でできるところまでやろうと思いました。ゲスト・ミュージシャンはエバートン・ネルソンとショーン・リーの二人だけですね。
エバートンとは、前作『to come...』で、すごく納得のいくものを作ることができたので次もまた彼と、よりスケールアップした形でやりたいと思っていたんです。
ヴォーカリストは最初、三人くらいにするつもりだったんです。作り手としてやりがいがあるし、聴く側にしても複数のヴォーカリストとの組み合わせを楽しむ人もいるだろうし。ところが、途中、アランから一人にしたほうがいいと言ってきました。いろんなヴォーカリストを入れると、サイレント・ポエツというイメージが散漫になってしまうから、一人に絞り込んだほうがいいんじゃないかと。あまり賛成ではなかったんですが最終的には納得しました。
実はすでにあるヴォーカリストでやることが決まっていたんです。でも、スケジュールの都合からギリギリのところで流れてしまった。そこで人選について再度、アランと相談したらショーンの名前を出してきたんですよ。ただ、僕自身はちょっと悩んだんです。彼の作品は素晴らしいけど当初の自分のイメージとは違う。そもそも彼のことを考えたことなんて一度もなかったんですからね。それをアランに伝えようとしたんですが、待てよ、と。合わないと思うからこそ、むしろいいんじゃないか、何より今回は今までと違うことをやろうとしてるんだから、と思ったんです。そう考え出したら、今度はむしろとてもいい人選のような気がしてきたんで、彼に決めました。アランは、あまりにスムースに、僕が了解したんで、意外そうだったけど。
前作でもそうだったんですが、デモテープを渡しただけです。そこに基本的なコードやメロを入れてあるので、それをベースにやってくれと頼みました。彼の場合、イメージと違うものをあげてくることはありませんし。
スタジオのブッキングからキャスティングまで、みなエバートンがやってくれました。レコーディングも調整する部分はありましたが、基本的には問題なく進みましたね。大満足です。
とりたてて意識していたわけではないですが、わからないではないですね。これまでのアルバムでは自分の感情をストレートに表現するのはどちらかといえば抑えてきたんです。ちょっと斜に構えてた部分もあったかもしれません。でも、いまはむしろ逆で、自分が生活する中で、感動したり、泣いたりするのは普通のこと。クサいって言われてもいい、むしろそういう気持ちを表に出したいって思ってましたから。それが自然と曲に現れるのかもしれませんね。
彼にも具体的には何も言っていないです。プロですから曲を聴けば自分が何をすべきかわかるはずです。デモを渡して、やりたいようにやってくれと。一ヶ月もしないうちに3曲が届きました。早かったですね。
すごく感動しました。それでいてキャッチーで覚えやすい、「いい曲」になったと思います。ショーンのほうも十分、満足していますね。
彼とは何度かデモ曲を渡して、さまざまなキャスティングのことから、いろいろ相談しつつやってきました。とにかく、今回は過去のポエツは卒業して次のステップに行くんだと何度も言われましたね。そんな彼の期待に応えなければと、常に思っていましたから気持ちの面でも励みになりました。レコーディングでは細かいところを補ってくれて様々なアイデアを出してきました。実際、アランのアイデアで曲がよくなることも多く、その都度、さすがだなと思いましたね。彼と組んだ事でサイレント・ポエツの違う魅力みたいなものが出たと思います。
前半はアランのスタジオで彼と編集作業をして、後半はパリ郊外にあるスタジオ、STUDIO DAVOUTに入って、アランは加わらずに、エンジニアのパスカルと作業しました。特にその後半のミックス・ダウンは本当にキツかったです。
パリでの作業には日本人スタッフが一人もいなかったことと、そもそもアルバム一枚すべてのミックスを海外でやるのは初めての経験でしたから。エンジニアのパスカルとももちろん初対面でそのペースに慣れるのがとにかく大変で。スケジュールもタイトでしたから休む間もほとんど無くストレスもたまるし、正直、逃げ出したかったです。過去に経験したレコーディング、特に日本でのレコーディングとは違いましたからね。
まあスケジュールやエンジニアにもよるんでしょうけど、スタジオに入る時間からして違いました。日本だとお昼から徐々にって感じですが、パリでは朝9時にはキッカリ、スタートしてました(笑)。終わりも早くてダラダラ深夜までやらないんです。それと一つ一つの作業に対し、その場で即、シロかクロかを決めないといけない。「とりあえず保留」ってのはなくて、とにかくすべてをどんどん明確にしながら進めて行く直感勝負なんですよ。基本的にはあれこれ悩んで後戻りしたりできませんでした。日本だと「なんか違うな」とか言って何度も何度も聴いたり1時間くらいお茶して考えたり、エンジニアにいろいろやってもらって、じゃあやっぱり最初に戻ろうかなんてやりとりがあったり、「う~ん、今日はもういいか。わかんなくなってきたから明日にしよう」なんてこともありますね(笑)。
 まぁ、一概にはどちらがいいとも言えないですが、その場その場で即判断しなきゃいけないのは相当にキツかったですね。毎日、朝から晩まで気が抜けない。延々とやってるから、精神的にすり減った感じしました。しかもスケジュールが決まっていて、毎日、予定通りに完成させないといけないから、そのプレッシャーもあったし。心身の疲れから、ホテルに戻った途端、毎日、バタン!って、倒れ込むように寝てしまっていましたよ。
近いかもしれません。でも、判断が早いから、音がとにかくハッキリしているんです。考えながらやると、どっちのつかずの音になっちゃうことが多いですからね。最初は強い印象にした音も、悩んだ末、抑えて普通にしたりとか。
そうですね。作品的にも非常に納得のいくものができました。特にショーンとエバートンとコラボレートした二曲(「Man On The Street」と「Dumb Girl」)は完璧ですよ。もうあれ以上は何もしようがないですから。
もちろん「to come...」など、これまでにもある程度の満足感を得るものはありましたが、完成度ではこの二曲にはかないません。アルバム全体を通せば、もちろん、粗も見えるし後悔もありますが、それでも一つ一つ、決して何となくというレベルで作ったわけじゃないので、ものすごく自分の中では納得しています。それとやっぱり、パリのスタジオでああいう作業をしたということは、今までとは違いよりヨーロッパの音楽の現場を肌で味わった気がして、それもよかったですね。
そうですね。新しいサイレント・ポエツは始まったばかりですから。いずれにせよ、今回は一人になってゼロから始めて、時間がかかったけど何とかやり遂げた。みんなとコラボレートできたし、パリでの作業もプラスになった。それで最終的に納得できるものが出来上がったのは自分にとって自信になりましたね。
まぁ、一概にはどちらがいいとも言えないですが、その場その場で即判断しなきゃいけないのは相当にキツかったですね。毎日、朝から晩まで気が抜けない。延々とやってるから、精神的にすり減った感じしました。しかもスケジュールが決まっていて、毎日、予定通りに完成させないといけないから、そのプレッシャーもあったし。心身の疲れから、ホテルに戻った途端、毎日、バタン!って、倒れ込むように寝てしまっていましたよ。
近いかもしれません。でも、判断が早いから、音がとにかくハッキリしているんです。考えながらやると、どっちのつかずの音になっちゃうことが多いですからね。最初は強い印象にした音も、悩んだ末、抑えて普通にしたりとか。
そうですね。作品的にも非常に納得のいくものができました。特にショーンとエバートンとコラボレートした二曲(「Man On The Street」と「Dumb Girl」)は完璧ですよ。もうあれ以上は何もしようがないですから。
もちろん「to come...」など、これまでにもある程度の満足感を得るものはありましたが、完成度ではこの二曲にはかないません。アルバム全体を通せば、もちろん、粗も見えるし後悔もありますが、それでも一つ一つ、決して何となくというレベルで作ったわけじゃないので、ものすごく自分の中では納得しています。それとやっぱり、パリのスタジオでああいう作業をしたということは、今までとは違いよりヨーロッパの音楽の現場を肌で味わった気がして、それもよかったですね。
そうですね。新しいサイレント・ポエツは始まったばかりですから。いずれにせよ、今回は一人になってゼロから始めて、時間がかかったけど何とかやり遂げた。みんなとコラボレートできたし、パリでの作業もプラスになった。それで最終的に納得できるものが出来上がったのは自分にとって自信になりましたね。