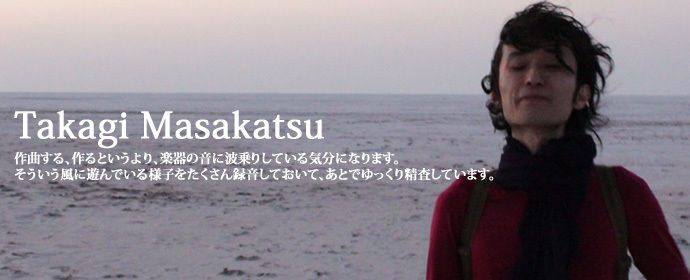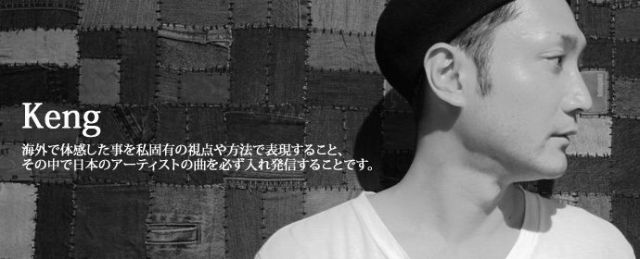ソロの作品を出す前は、AOKI takamasa君とSILICOMというユニットを組んで2年程活動していました。僕は映像担当で。クラブに呼ばれてVJをやったりもしました。 頭の中にある音や絵をどうやったら作れるのか、試行錯誤の繰り返しで、目標や夢というものを考えたこともありませんでした。いまも同じような感じです。こういうのを作ってみたいとか、こういう暮らしにしていこうという想いはいつもありますが…。
ソロの作品を出す前は、AOKI takamasa君とSILICOMというユニットを組んで2年程活動していました。僕は映像担当で。クラブに呼ばれてVJをやったりもしました。 頭の中にある音や絵をどうやったら作れるのか、試行錯誤の繰り返しで、目標や夢というものを考えたこともありませんでした。いまも同じような感じです。こういうのを作ってみたいとか、こういう暮らしにしていこうという想いはいつもありますが…。
 10年ほどずっと変わっていません。食べて寝て、作って作って作って、遊んで遊んで。
30歳を超えてから随分と変わった気がします。小学生の頃に戻ったような。年々ずいぶん気楽になっているなと思ってます。
その人が見いだした豊かさを表に出せたものは何でも好きです。苦手なのはその逆です。
みんな元気で楽しくやっているときです。
単純にピアノが下手だったからです(いまでも下手ですが)。ずっとピアノの音が好きで、演奏するのが好きで、だけどピアノで曲を作るというのがいまいちよく分からなかったんです。電子音だと、とても気楽で。現象を見ているだけでいいというか、カメラの撮影に似ていて、どの瞬間をどう捉えるかということに集中していれば曲が作れました。曲の作り方がわかったので、それをピアノに置き換えていっている感じです。
2003年辺りは音楽を作っている気持ちはほとんどなくて、あくまで映像が主体で、おまけで音楽を作っている感覚でした。なので、ほんとうに気楽だったんだと思います。今でも、暇があれば何か作っていますが、あの時に比べるともう少し時間を掛けて作り込むようになりました。本当は写真と同じで、演奏したその時間がそのまま収まっているのが音楽の1番いい形だと思っていて、それだと5分演奏したら、その場で5分の曲になりますよね? そういう作り方が理想です。なので、以前に比べたら制作時間の他に、練習する時間が増えました。
あの出来事から受け取った様々な感情をそのまま表に出すのが、自分の仕事だと思って、正直にそのまま演奏しました。舞台の上では、それしかできませんし、逆にあの場所で表に出せないなら意味がないなと、とても張りつめた想いで舞台に立ったのを覚えています。
10年ほどずっと変わっていません。食べて寝て、作って作って作って、遊んで遊んで。
30歳を超えてから随分と変わった気がします。小学生の頃に戻ったような。年々ずいぶん気楽になっているなと思ってます。
その人が見いだした豊かさを表に出せたものは何でも好きです。苦手なのはその逆です。
みんな元気で楽しくやっているときです。
単純にピアノが下手だったからです(いまでも下手ですが)。ずっとピアノの音が好きで、演奏するのが好きで、だけどピアノで曲を作るというのがいまいちよく分からなかったんです。電子音だと、とても気楽で。現象を見ているだけでいいというか、カメラの撮影に似ていて、どの瞬間をどう捉えるかということに集中していれば曲が作れました。曲の作り方がわかったので、それをピアノに置き換えていっている感じです。
2003年辺りは音楽を作っている気持ちはほとんどなくて、あくまで映像が主体で、おまけで音楽を作っている感覚でした。なので、ほんとうに気楽だったんだと思います。今でも、暇があれば何か作っていますが、あの時に比べるともう少し時間を掛けて作り込むようになりました。本当は写真と同じで、演奏したその時間がそのまま収まっているのが音楽の1番いい形だと思っていて、それだと5分演奏したら、その場で5分の曲になりますよね? そういう作り方が理想です。なので、以前に比べたら制作時間の他に、練習する時間が増えました。
あの出来事から受け取った様々な感情をそのまま表に出すのが、自分の仕事だと思って、正直にそのまま演奏しました。舞台の上では、それしかできませんし、逆にあの場所で表に出せないなら意味がないなと、とても張りつめた想いで舞台に立ったのを覚えています。
 変化はたくさんあります。随分変わったと思います。1番大きいな変化は、自分が知っている豊かさ、自分の周りにある豊かさをきちんと表現したいと思うようになったことです。
よく訊かれるのですが、特に理由はありません。撮影してきたものを見てみると、だいたい子どもか女性を撮影していることに気付きます。旅先で撮影することが多いので、日中、外に出ているのが子どもや女性ということなんだと思ってます。あとはやはり、動きのある映像が好きなので、子どもが爆発的に動き回ってくれると、ついつい撮影して作品に仕上げたくなります。
ここ1年映像を作っていないので、随分過去のことになってしまっていますが、毎回、新たな手法を探るところからスタートさせています。見たことの無いような画面が出てきたら、そこから先、どんどん膨らませていって、その時それ以上は考えられないところまで最初に発見した手法を発展させていきます。作る内容は毎回違うので、なんともいえませんが、それまでに読んだ本や旅先で感じたことなど、人や場所から影響を受けて作っています。作り始めると、最終的にどういう作品になるのか、自分でも全くわかっていないので、迷ったり止まったりする度に、人と話をしたり、本を探したり、自分の方向性を見定めています。
映像だと撮影してきた素材があったりするので、まったく何もないところから作る訳ではありません。音楽の場合も、映画音楽やCM音楽をたくさんやらせて頂きましたが、そういう場合は、映像やコンテがあるので、向うべき方向は掴みやすいです。ただ、個人的に音楽を作るとなると…、もう思い付くとしかいいようがないです。ピアノや色んな楽器で遊んでいる最中におもしろい響きを見つけて、そこからメロディーを探していったり。最近は演奏しながら歌うことがことが多くなりました。歌っていると自然と湧いてくる旋律があって。特に楽器を演奏しながら歌っていると、作曲する、作るというより、楽器の音に波乗りしている気分になります。そういう風に遊んでいる様子をたくさん録音しておいて、あとでゆっくり精査しています。いい旋律や響きがあったら、そこを紡いでいって曲に仕上げることが多くなりました。
2003年頃にDavid Sylvianさんのヨーロッパツアーに参加したのですが、彼の自宅で2週間ほどリハーサルがありました。そのときは彼のコンサートに映像をつける役割だったのですが、みんなが寝静まった真夜中にピアノが弾きたくなって。スタジオにおいてあった電子ピアノで演奏したら、面白い感じの曲ができそうだったので、すぐに手元にあったビデオカメラで録音して。ツアーから日本に戻るころには自分のソロコンサートを控えていて、新しい曲を用意しなければいけなかったんですね。そこで、録音した曲をなんとか仕上げられないかと四苦八苦しているうちに、早送りのボタンを押してしまったんです。するとゆっくり弾いていた演奏が倍速だと、聴いたことがないようなピアノの曲になって。Girlsは代表曲になりましたが、作曲した経緯は、情けないくらい偶然の連続で。でも、自分にとってもいい曲が生まれる時って、案外そういう形でふわっと出てくるものかもしれませんね。
変化はたくさんあります。随分変わったと思います。1番大きいな変化は、自分が知っている豊かさ、自分の周りにある豊かさをきちんと表現したいと思うようになったことです。
よく訊かれるのですが、特に理由はありません。撮影してきたものを見てみると、だいたい子どもか女性を撮影していることに気付きます。旅先で撮影することが多いので、日中、外に出ているのが子どもや女性ということなんだと思ってます。あとはやはり、動きのある映像が好きなので、子どもが爆発的に動き回ってくれると、ついつい撮影して作品に仕上げたくなります。
ここ1年映像を作っていないので、随分過去のことになってしまっていますが、毎回、新たな手法を探るところからスタートさせています。見たことの無いような画面が出てきたら、そこから先、どんどん膨らませていって、その時それ以上は考えられないところまで最初に発見した手法を発展させていきます。作る内容は毎回違うので、なんともいえませんが、それまでに読んだ本や旅先で感じたことなど、人や場所から影響を受けて作っています。作り始めると、最終的にどういう作品になるのか、自分でも全くわかっていないので、迷ったり止まったりする度に、人と話をしたり、本を探したり、自分の方向性を見定めています。
映像だと撮影してきた素材があったりするので、まったく何もないところから作る訳ではありません。音楽の場合も、映画音楽やCM音楽をたくさんやらせて頂きましたが、そういう場合は、映像やコンテがあるので、向うべき方向は掴みやすいです。ただ、個人的に音楽を作るとなると…、もう思い付くとしかいいようがないです。ピアノや色んな楽器で遊んでいる最中におもしろい響きを見つけて、そこからメロディーを探していったり。最近は演奏しながら歌うことがことが多くなりました。歌っていると自然と湧いてくる旋律があって。特に楽器を演奏しながら歌っていると、作曲する、作るというより、楽器の音に波乗りしている気分になります。そういう風に遊んでいる様子をたくさん録音しておいて、あとでゆっくり精査しています。いい旋律や響きがあったら、そこを紡いでいって曲に仕上げることが多くなりました。
2003年頃にDavid Sylvianさんのヨーロッパツアーに参加したのですが、彼の自宅で2週間ほどリハーサルがありました。そのときは彼のコンサートに映像をつける役割だったのですが、みんなが寝静まった真夜中にピアノが弾きたくなって。スタジオにおいてあった電子ピアノで演奏したら、面白い感じの曲ができそうだったので、すぐに手元にあったビデオカメラで録音して。ツアーから日本に戻るころには自分のソロコンサートを控えていて、新しい曲を用意しなければいけなかったんですね。そこで、録音した曲をなんとか仕上げられないかと四苦八苦しているうちに、早送りのボタンを押してしまったんです。するとゆっくり弾いていた演奏が倍速だと、聴いたことがないようなピアノの曲になって。Girlsは代表曲になりましたが、作曲した経緯は、情けないくらい偶然の連続で。でも、自分にとってもいい曲が生まれる時って、案外そういう形でふわっと出てくるものかもしれませんね。いろんな背景がありすぎて、どこから話せばいいのか分からなくなってしまいますが。単純にいうと、自分なりに感じてきた、日本で生まれて日本で生活しているのに、ピアノを弾いていること、西洋の調律、響きで音楽を奏でていることの不思議さ、違和感をどうにか自分に納得させたくて、臨んだんだと思います。Tai Rei Tei Rioのプロジェクトを通して、昔のことをきちんと学んで受け継ぎたいという姿勢が身にしみたと思います。
 子どもの頃からそうですが、誰かに聴いて欲しくて音を奏でてきました。なので、自分の音楽を喜んでもらえると、とても嬉しいです。もうほんとうにそれしかなくて。聴いてもらえる相手は人じゃなくても、例えば、庭にやってきた鳥でも、向こうに見える山でも、風でも、一緒に「こういう響きはどう? こうやったら違うところにいったね」と、その時間を豊かに楽しめたら、それでいいと思ってずっと生活してきました。何を表現したいかというと、もう自分が発見した豊かさということにつきます。それを届けたいし、僕も受け取りたい。とても単純な想いです。
先にも話しましたが、ほんとうに求めているのは、その5分で起こったことが、そのまま届けられることなんです。あと、舞台にあがると、やはり家やスタジオにいる時とはまるで違う空気に包まれるので、その緊張感の中で生み出されるものに興味があります。とはいえ、常にコンサートからCDという流れを考えている訳でもなくて、Private/PublicとTai Rei Tei Rioはたまたまそういうタイミングだったのだと思ってます。
子どもの頃からそうですが、誰かに聴いて欲しくて音を奏でてきました。なので、自分の音楽を喜んでもらえると、とても嬉しいです。もうほんとうにそれしかなくて。聴いてもらえる相手は人じゃなくても、例えば、庭にやってきた鳥でも、向こうに見える山でも、風でも、一緒に「こういう響きはどう? こうやったら違うところにいったね」と、その時間を豊かに楽しめたら、それでいいと思ってずっと生活してきました。何を表現したいかというと、もう自分が発見した豊かさということにつきます。それを届けたいし、僕も受け取りたい。とても単純な想いです。
先にも話しましたが、ほんとうに求めているのは、その5分で起こったことが、そのまま届けられることなんです。あと、舞台にあがると、やはり家やスタジオにいる時とはまるで違う空気に包まれるので、その緊張感の中で生み出されるものに興味があります。とはいえ、常にコンサートからCDという流れを考えている訳でもなくて、Private/PublicとTai Rei Tei Rioはたまたまそういうタイミングだったのだと思ってます。
 難しい問題ですね。見たり聴いたりに関しては、僕の場合、学校以外のところで親やピアノの先生などが色々と連れていってくれたので、特に不満もないまま、子ども時代をおくれた気がします。義務教育の小学校、中学校と音楽や美術の授業は楽しかったですし、色んなものを知れたのでそれはそれでよかったんじゃないかと思ってます。仮に自分が授業を受け持ったとしたら、別のアプローチで子どもたちと接すると思いますが。最近は、近くの幼稚園に遊びに行く機会が増えて、ときには楽器を持っていって演奏したりもします。子どもはある程度、音の鳴らし方がわかったら自分たちで工夫して遊び出しますから、こちらは教えるというより、見守ることしかできませんし、それでいいなと思いました。現場で聴くという体験も大切ですが、やはり自分も奏でたり描いた方が楽しいと思うので、こういうやり方があるよというのを提示して刺激しながら、その場で生まれてくる発想でどこまでいけるか一緒に楽しむことも大事だと思います。受けとる体験も大切ですが、自分の中にあるものを表に出す喜びを知る体験も大切です。
会場と同時に自分の番が始まるので、どうしようかと悩んでいます。はじめてのシチュエーションなので…。きっと僕の時間は、他の人からそうとう浮いた時間になると思いますが、自分がやれること、やりたいことは既に持っているので、素直に楽しもうと思っています。
10年前、SILICOMというユニットをAOKI takamasa君と組んで活動していたときであれば、とても身近なラインナップになっていたのかなと思いました。もう10年以上、クラブには足を踏み入れていませんし、そこで流れている音楽も耳にしていません。なので、正直なところ、自分によく声が掛かったものだと不思議に思っています(笑)。他のアーティストの方々の音は自分にとても新鮮に響くものばかりだと思うので、とても楽しみにしています。
開場されたと同時にライブをはじめると思います。自分の番がどのような形ではじまり終わっていくことになるのか、想像しようがありませんが、ぜひお早めに会場に足を運ばれて下さい。お待ちしております!
開催日:東京・11月23日(金・祝日) 大阪・11月24日(土)
難しい問題ですね。見たり聴いたりに関しては、僕の場合、学校以外のところで親やピアノの先生などが色々と連れていってくれたので、特に不満もないまま、子ども時代をおくれた気がします。義務教育の小学校、中学校と音楽や美術の授業は楽しかったですし、色んなものを知れたのでそれはそれでよかったんじゃないかと思ってます。仮に自分が授業を受け持ったとしたら、別のアプローチで子どもたちと接すると思いますが。最近は、近くの幼稚園に遊びに行く機会が増えて、ときには楽器を持っていって演奏したりもします。子どもはある程度、音の鳴らし方がわかったら自分たちで工夫して遊び出しますから、こちらは教えるというより、見守ることしかできませんし、それでいいなと思いました。現場で聴くという体験も大切ですが、やはり自分も奏でたり描いた方が楽しいと思うので、こういうやり方があるよというのを提示して刺激しながら、その場で生まれてくる発想でどこまでいけるか一緒に楽しむことも大事だと思います。受けとる体験も大切ですが、自分の中にあるものを表に出す喜びを知る体験も大切です。
会場と同時に自分の番が始まるので、どうしようかと悩んでいます。はじめてのシチュエーションなので…。きっと僕の時間は、他の人からそうとう浮いた時間になると思いますが、自分がやれること、やりたいことは既に持っているので、素直に楽しもうと思っています。
10年前、SILICOMというユニットをAOKI takamasa君と組んで活動していたときであれば、とても身近なラインナップになっていたのかなと思いました。もう10年以上、クラブには足を踏み入れていませんし、そこで流れている音楽も耳にしていません。なので、正直なところ、自分によく声が掛かったものだと不思議に思っています(笑)。他のアーティストの方々の音は自分にとても新鮮に響くものばかりだと思うので、とても楽しみにしています。
開場されたと同時にライブをはじめると思います。自分の番がどのような形ではじまり終わっていくことになるのか、想像しようがありませんが、ぜひお早めに会場に足を運ばれて下さい。お待ちしております!
開催日:東京・11月23日(金・祝日) 大阪・11月24日(土)時間:両日とも21時オープン
東京:【HALL 9】Flying Lotus, Squarepusher, Amon Tobin ISAM, Tnght, DJ Krush, Kode9, 【HALL 11】電気グルーヴ, ORBITAL, Four Tet, Andrew Weatherall, NATHAN FAKE, DJ Kentaro, 高木正勝, 【SPECIAL GUEST】DAITO MANABE
大阪:FLYING LOTUS, ORBITAL, SQUAREPUSHER, FOUR TET, ANDREW WEATHERALL, TNGHT, NATHAN FAKE, KODE9
■オフィシャルサイト
http://www.electraglide.info/