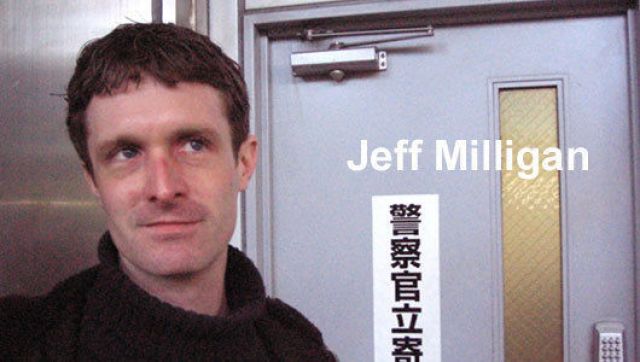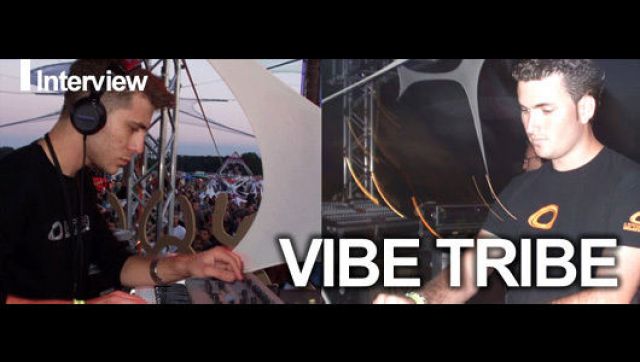音楽って純粋にクリエイトされたものの中からしか「本物」が生まれないって思われがちなんだけど、そもそもダンスミュージックって虚構の中における幻みたいな部分ってあるじゃない。最近特にそういう実体のないものこそが、実はリアルなんだと思っていて、このリアリティーをどうしたら音楽作りに投影できるのかについてはけっこう真剣に考えている。ただし、アルバムは俺にとっての「作品」なので、クラブでバカ騒ぎをする自分と混同してはいけないとも思っている。もちろんダンスフロアも好きだし、 マジメにDJとしてやるべきことはやっているけどね。
DJとしてのFPMの「ドカーン!」とアゲな部分ばかりを集めたCDってのもアリだとは思うけど、そういうものにしたくないという気持ちも働き、今回はダンスミュージックがあえてスポイルしてきた「インテリジェンス」+「アカデミズム」みたいな部分を引き受けた作品にした。といっても別に頭のいい人に聞いて欲しいってことではないんだけどね。
ダンスフロアというのは「FPM」を形作るものとして不可欠な要素なので、今回のアルバムもフロアに持っていけば確実に武器になるものに仕上がっている。ただ、いつも思うのはCDってのは「作り手」の僕と「聞き手」の誰かの一対一の人間関係を見据えたものでなければならないってこと。
たとえばトランスのミックスCDで、3000人とか1万人とかの大観衆の前でかけることを前提にしたものは、それよりも小さい場所、たとえば家なんかで聞くと違和感を感じることってあるでしょ? 自分でも最近はレコード屋で売ってるCDについて「完璧」に満足できるものって少なくて、クラブでDJとしてプレイするときはバッチリ機能する曲でも、それ以外のときに聞きたくなるかというとそうじゃないことも多い。いつもアルバムを作るにあたっては、メジャーからCDを出すアーティストの自覚として、その辺は考えなければいけないと思ってるんだ。
 派手に見えるかもしれないけど、音楽もファッションも実は厳しい世界だから、「一夜の喧騒」的なノリだけで、調子にのったものを作ると必ず足元をすくわれる。クリエイティビティーにおいても先端的なものでないと、音楽シーン全体としては納得してくれないんだ。偉そうぶるつもりはないけど、10年もやってるとちょっとやそっとじゃ、まわりもなかなか作品として「すげえ」なんて思ってくれないし、自分自身のハードルもどんどん高くなっていく。だから、それを超えていけるトラックしか残らないんだよね。誤解を恐れずに言えば、刹那的な流行と添い寝した音楽がダンスミュージックの本分だとしても、それだけではない作品を作りたいと思う。さまざまな流行の音があったとしてもそれに対してFPMとして答えを出しつつ、「その次」を狙っていかなければならないし。
派手に見えるかもしれないけど、音楽もファッションも実は厳しい世界だから、「一夜の喧騒」的なノリだけで、調子にのったものを作ると必ず足元をすくわれる。クリエイティビティーにおいても先端的なものでないと、音楽シーン全体としては納得してくれないんだ。偉そうぶるつもりはないけど、10年もやってるとちょっとやそっとじゃ、まわりもなかなか作品として「すげえ」なんて思ってくれないし、自分自身のハードルもどんどん高くなっていく。だから、それを超えていけるトラックしか残らないんだよね。誤解を恐れずに言えば、刹那的な流行と添い寝した音楽がダンスミュージックの本分だとしても、それだけではない作品を作りたいと思う。さまざまな流行の音があったとしてもそれに対してFPMとして答えを出しつつ、「その次」を狙っていかなければならないし。自分が大ブームを作ってやろうとか、流行に身を投じてイニシアティブを取ってやろうとかいうのは昔から考えていなかったけど、FPMとして独自の存在感があって、独自の風合いのトラックを作り続けることと、ワンアンドオンリーであること、そしてそれをずっと継続していくことってのは、本当に難しいことだけど、大事にしている。
実は、作品として地に足つけて誰もが納得いくものを作ろうと努力することこそが、クラブでの「一夜のバカ騒ぎ」の原動力にもなっているし、だからこそバカなことをやってても胸を張っていられるっていう部分もあるしね。
 いまって、「本当に新しい」ものは出しにくい世の中だと思うんだよね。世の中の人が評価や気分がものすごく1つの方向を向いてるって気がする。そのなかで自分の独自性を高めていくのってすごい困難なことだと思う。
いまって、「本当に新しい」ものは出しにくい世の中だと思うんだよね。世の中の人が評価や気分がものすごく1つの方向を向いてるって気がする。そのなかで自分の独自性を高めていくのってすごい困難なことだと思う。たとえば、2、3年前だったら、EMMA君と大沢君と卓球君とツヨシ君とトミイエさんと俺とスギウラムってかなり独自の選曲なので、レコードバッグの中がかぶることなんて、考えられなかったんだけど、いまはドイツ系のアバンギャルドなテクノとかが最大公約数的な音になってきていて、1、2枚はかぶってる気がする。これはウラを返せば、それだけ、いいトラックが生まれていないってことなのかもしれない。
海外ではまだムーブメントを起こせる土壌がダンスミュージックにあると思うけど、国内ってまだDJ文化というかダンスミュージックに対するプライオリティーが低いって感じるときがあるし、東京にいたっては18、19歳の音楽にもっとも多感な年齢の人がクラブに入れないっていう、ありえない状況だよね。クラブが犯罪の温床になってるっていう人もいるけど、実際はそんなことないし、悪いやつなんてのはどこに行っても悪いことしてるわけだから、それぞれの自覚でしかない。ロックフェスでもダンステントって端っこにあったりするしね。そういう状況をなんとかしたいけど、何をしたらいいのかってジレンマはあるんだよね。
今回のアルバムを振り返ってみると、そういう不安や不満が前提にあって、自分としても何を作るべきかという思いやネガティブなパワーもひっくるめて、作品作りに転嫁していくって作業でもあった気がするな。
 今回のアルバムでは歌詞も1曲以外はすべて自分で手がけた。LAのUgly Ducklingってラップチームとの曲だけは彼らに任せたんだけど、それでもテーマは確実に伝えたし、それに準じたリリックができあがってきて、満足してる。
今回のアルバムでは歌詞も1曲以外はすべて自分で手がけた。LAのUgly Ducklingってラップチームとの曲だけは彼らに任せたんだけど、それでもテーマは確実に伝えたし、それに準じたリリックができあがってきて、満足してる。作詞は1回日本語で書いて、それを英訳してもらったのものを、さらに微調整していくので、めんどくさいんだけど、歌詞の世界まで目を光らせていかないと作品としてはヤバイし、トータルな世界観を大事にしたいから、英語のできる歌手に歌詞まで丸投げ、ってのはしたくなかったんだよね。
ダンスミュージックでは歌詞がトラックに対してオマケみたいな部分もあるし、リフレインがダンスフロアにおいて、有効なこともわかってるけど、自分としてはそれに対する違うアプローチとして、踏み込んだリリックの世界を表現したいと思ったんだ。
一方、ゲストについては、FPMって基本的に1人だからいろんな人の協力が必要だってのが前提にあった上で、今回は自分とのコラボレーションが「必然」である人、「運命の人」と一緒に仕事したいっていう想いがあった。
BONNIE PINKは自分がDJを始めたばかりのころ、まだ5人しかお客さんがいないようなとき当時京都の大学に通う学生だった皆が遊びに来てくれてたという縁だし、RIP SLYMEのSU君については彼らのデビュー前にプロデュースをしたという縁がある。韓国のCLAZZIQUAI PROJECTは向こうでは大スターなんだけど、留学先のカナダで僕の音楽を聴いて音楽を始めたんだって明言してくれたんだ。また、TAHITI 80も僕の「Why not?」って曲をメンバーがホテルで何度も聴いてくれていたのが縁で仲良くなった。一方、Benjamin Diamondは僕にとっては昔からスターダストのころからの憧れのスターだったからね。
思い入れのある曲ということでは、Lil Louisの「French Kiss」は自分がハウスを好きになるきっかけの曲だったし、なんとかカバーしたいと思っていたんだけど、アレを全部、生楽器に置き換えるというアイデアが浮かんだときには自分でひざを打ったね! この曲に関してはだんだん上がったり下がったりするテンポ自体が作曲だと思ったので、そうした点や、原曲の不思議な空気感までしっかり再現するように努めたよ。だから、そうした点も聞いてもらえるとうれしいね。
こうして自分にとって縁のある人、個人的につながりがあって、わかり合ってる人とやるってことも、やはり作品に僕自身の「リアリティー」を与えることに結び付くと思うんだ。
 今回は非常にストイックに生みの苦しみを感じたりしながら、自分なりに非常に満足できるいい作品ができたので、もうここまでやったら次は何をやってもいいかなって思えるところまで、ようやくたどり着けた。だから、次はかなり自由に、あり得ないくらいベタなことや、俗っぽいこと、イージーなことをやったとしても、許してくれるんじゃないかなーってね。今回の作品を作ったことでやっとそう思えるようになってきたので、次はそういう大胆なアイデアも含めて、よりおもろいことをやっていきたいな。
今回は非常にストイックに生みの苦しみを感じたりしながら、自分なりに非常に満足できるいい作品ができたので、もうここまでやったら次は何をやってもいいかなって思えるところまで、ようやくたどり着けた。だから、次はかなり自由に、あり得ないくらいベタなことや、俗っぽいこと、イージーなことをやったとしても、許してくれるんじゃないかなーってね。今回の作品を作ったことでやっとそう思えるようになってきたので、次はそういう大胆なアイデアも含めて、よりおもろいことをやっていきたいな。