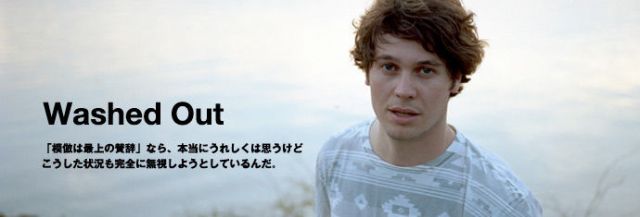レーベル第1弾のこの「HOUSE CLAPPERZ VOL.1」は、今年の2月から"MICROCOSMOS"でスタートしたパーティーとも連動していて、コンセプトは「自分たちの遊べる場所を作りたい」っていうところから始まってるんですけど。もうひとつは、自分的にはクラブの理想って90年代に行ったニューヨークのクラブだと思ってるところがあって。それって、ダンサーも踊ってるけど、普通のお客さんもちゃんと踊って楽しんでる感じで。なんかキラキラしたところもよかったし、かかってる曲もすごいカッコよくてみたいなのが、自分のクラブへの憧れだったりとかしてて。今までで一番カッコイイと思ったものがそのスタイルだったから、そういうパーティーをまたちゃんとやりたいと思ったんですよ。
 そうなんです、ちょっと賛否両論あるとは思うんですけど。なんで限定かというと、やっぱりちゃんと自分たちの遊び場を確保したいというのと、DEXPISTOLSだったりとかエレクトロだったりを期待してもらって来られても、っていうか。僕のソロのDJはそういうことをやろうとは思ってなくて、あえて別なことをやろうとも思ってないんだけど、でもそれは別に最先端というわけでもなく、昔の音楽も含めて、自分がおもしろいと思える音楽でDJやりたいなという感じで考えてるんで。ちょっと限定にしたりとか、人数制限かけてるのは、やっぱり入り過ぎて踊れなくなるのも嫌だし……。まぁ単純にワガママなパーティーとしてやってる感じです。
やっぱり基本的に、エレクトロだったりとかDEXPISTOLSのDJって、グルーヴを止めて盛り上げたりとかっていう、ちょっとライブ感がおもしろかったりするんだと思うんですよ。なんかそういうのじゃなくて、ホントに踊ってる人の足が止まらない、踊り続けられるフロアを作りたくて。ハウスだけをかけるというわけじゃなく、ダブステップもかけるし、UKベースもかけるんですけど。やっぱりハウスミュージックというものの一番の魅力というのは、足が止まらないというところだと思うんで、このパーティーはそこをキーワードにしてやっていきたいですね。
(笑)そうですね、やっぱりDEXPISTOLSって楽曲も含めて、自分が思ってるより大きな存在になったと思うんですよ。でも結局最終的に、自分がそこと対決しなきゃいけないんだなと思ってる。もちろんDJ MAARに対しても同じようにそれだけのイメージを持ってる人もいるじゃないですか。DEXPISTOLSってもののイメージに対して、それを超えられるくらいの自分「DJ MAAR」というのを作り上げたいということですよ。それには、やれることを自分がやらないといけないのかなとか。その流れで、DEXPISTOLSって僕の性格もDARUMAくんの性格もあって、流行りものに対して敏感っていうか、右往左往するところがあって(笑)。まぁ、DEXPISTOLSはそういう役割だと思ってるので、それでいいと思うんですけど、そうじゃない普遍的なものもやりたいと思ってて。要は東京からきちんとしたオリジナルのものを作って、発信することなんですが、ダンスミュージックの性だったりDJの性だったりもあるんですけど、日本ってとくに流行りものに対して過敏なところってあるじゃないですか。それをやってるうちは、日本では一個の大きいシーンは作れないだろうなと。ベルリンの話じゃないけど、実際何が起こってるかわからないけど、なぜか世界中が注目してるみたいな。でも「ベルリンのローカルDJって誰?」ていうと案外知らなかったりとか。ベルリンだけでまわっちゃってるシーンがあるんですよね。ちゃんとおカネにもなってるし、ご当地でガッツリやれてるものは、大きなエネルギーを持ったものを作れるんじゃないかってね。
そうですね。そんなところから半径狭く、近いところでシーンを作っていきたいなと思って。みんなネットで掘ってたりとか、海外のブログに迎合し過ぎてたりとかっていうのに、ちょっとアンチを唱えたい部分もあったりするし。いわゆるエレクトロを期待してる人たちに対して、ミックスCDではわざとああいうチョイスをして、僕的には10年先まで聴けるマスターピースを選んだつもりだし。
そうなんです、ちょっと賛否両論あるとは思うんですけど。なんで限定かというと、やっぱりちゃんと自分たちの遊び場を確保したいというのと、DEXPISTOLSだったりとかエレクトロだったりを期待してもらって来られても、っていうか。僕のソロのDJはそういうことをやろうとは思ってなくて、あえて別なことをやろうとも思ってないんだけど、でもそれは別に最先端というわけでもなく、昔の音楽も含めて、自分がおもしろいと思える音楽でDJやりたいなという感じで考えてるんで。ちょっと限定にしたりとか、人数制限かけてるのは、やっぱり入り過ぎて踊れなくなるのも嫌だし……。まぁ単純にワガママなパーティーとしてやってる感じです。
やっぱり基本的に、エレクトロだったりとかDEXPISTOLSのDJって、グルーヴを止めて盛り上げたりとかっていう、ちょっとライブ感がおもしろかったりするんだと思うんですよ。なんかそういうのじゃなくて、ホントに踊ってる人の足が止まらない、踊り続けられるフロアを作りたくて。ハウスだけをかけるというわけじゃなく、ダブステップもかけるし、UKベースもかけるんですけど。やっぱりハウスミュージックというものの一番の魅力というのは、足が止まらないというところだと思うんで、このパーティーはそこをキーワードにしてやっていきたいですね。
(笑)そうですね、やっぱりDEXPISTOLSって楽曲も含めて、自分が思ってるより大きな存在になったと思うんですよ。でも結局最終的に、自分がそこと対決しなきゃいけないんだなと思ってる。もちろんDJ MAARに対しても同じようにそれだけのイメージを持ってる人もいるじゃないですか。DEXPISTOLSってもののイメージに対して、それを超えられるくらいの自分「DJ MAAR」というのを作り上げたいということですよ。それには、やれることを自分がやらないといけないのかなとか。その流れで、DEXPISTOLSって僕の性格もDARUMAくんの性格もあって、流行りものに対して敏感っていうか、右往左往するところがあって(笑)。まぁ、DEXPISTOLSはそういう役割だと思ってるので、それでいいと思うんですけど、そうじゃない普遍的なものもやりたいと思ってて。要は東京からきちんとしたオリジナルのものを作って、発信することなんですが、ダンスミュージックの性だったりDJの性だったりもあるんですけど、日本ってとくに流行りものに対して過敏なところってあるじゃないですか。それをやってるうちは、日本では一個の大きいシーンは作れないだろうなと。ベルリンの話じゃないけど、実際何が起こってるかわからないけど、なぜか世界中が注目してるみたいな。でも「ベルリンのローカルDJって誰?」ていうと案外知らなかったりとか。ベルリンだけでまわっちゃってるシーンがあるんですよね。ちゃんとおカネにもなってるし、ご当地でガッツリやれてるものは、大きなエネルギーを持ったものを作れるんじゃないかってね。
そうですね。そんなところから半径狭く、近いところでシーンを作っていきたいなと思って。みんなネットで掘ってたりとか、海外のブログに迎合し過ぎてたりとかっていうのに、ちょっとアンチを唱えたい部分もあったりするし。いわゆるエレクトロを期待してる人たちに対して、ミックスCDではわざとああいうチョイスをして、僕的には10年先まで聴けるマスターピースを選んだつもりだし。DEXも最初はクラブ業界だったり、DJ業界だったり、レコ屋だったりのアンチだったんですけど。というのも、そのフィルターを通されて入ってきたものをリスナーは聴いてるわけで、そのフィルターを通さないっていうか、そういう人達が選ばないものをあえて選ぶようにしてたんです。そこは自分たちにすごく自信があった部分だし、「超ハイプだけどおもしれーじゃん!」みたいなところから始まってたんですけど、いつしかエレクトロってエッジーなものではなくなって、むしろメインストリームなものになってきちゃって……、いつの間にかJ-POPみたいな枠に入ってるし。「ぶちアゲでしょー!」みたいに言われてるのもねぇ……。もちろんフロアはぶちアゲてたけど、はなからそんなぶちアゲてる曲をかけてたわけじゃなかった気もするし。そのぶちアガってた感じに僕らは魅力を感じてたわけじゃなくて、それがあまりにも大衆化みたいになってきたときに、僕も周りもおもしろ味を感じなくなってきて、気が付いたら「俺何のために?」って思ってきて。でも、もちろんDEXPISTOLSっていうのはそういうものも求められてて、そういうことに対しても答えを出さないといけないと思ってるんですけどね。でも僕個人は返す必要もないんじゃないかと。僕的にはノリで「わーっ!」と盛り上がってるよりも、ブレイクのときに小声で「この曲ヤベー!」って言ってる若者がいる方が、けっこうアガったりするんですよね(笑)。僕自身がそういう人間だったし、最終的には、自分がホントに好きなものってカッコイイってものよりも、「うわヤベー!」って思うものが多いんですよ。 イメージは、そうですね。最近のベースミュージックにはすごい興味があるし、プレイもするんですけど、遊んでる若い子たちもその辺の音は聴いてるだろうと思ってて。だったらそこを繋いじゃっても、おもしろいんじゃないかっていうのと、タイムレス、時代感がわからないものをどうしても(!)作りたくて。普遍的なものってある種、時代感がわからないものが多いんですよ。それこそ「これが新しいです!」っていってるものってすごいクラシックな要素が絶対入ってるんですよ。それはシカゴジュークであったりとかダブステップだったりとかなんですけど。それがちょっと僕的にはおもしろくて。時代感がわからないもの、何年代ってわからないものがやりたくて。単なる"バックトゥ90's"みたいなものにもしたくなかったし。「クラシックに新しい要素を入れるとニュークラシック的なものが作れる」ってPHENOMENONのオオスミくんが雑誌のインタビューで言ってたんですけど。「あっ、俺のやりたいことってそれなんだな」みたいな。
でも、自分のオリジナルを作りたいと思ったときに、結局自分のオリジナルはどこにあるんだろうって考えると、「自分のオリジナルって実は自分の恥ずかしい部分にあって、でもそれは一周まわらないと理解できないし、許せない」という話を誰かがツイートしてて、いいこと言ってるなぁと思って。で、結局開き直ったところをやってみようかなと思ったんです。ひとりだしね。ここでまた僕が今のその「これが新しいです!」ってレースに参加したら何も変わらないなと思うんですよね。
DEXPISTOLSってものもやってて、ここでエレクトロハウスのミックスを作ったところで、どうせ若い子に「アゲでしょ!?」って言われるみたいな、逆に刺さらないと思ったんですよ。いろんな意味で攻めてるんだなって姿勢を見せたいっていうか、示したいなと。それこそ極論言えば理解されなくてもいいし、エレクトロってもので「DEXPISTOLSが好きでアゲなのが好きですっ!」ていう層には理解されなくてもいいけど、自分なりに攻めた姿勢ってものを提示したかったんです。 めちゃめちゃ考えてますよ!考え過ぎとか思っちゃいますけど。その挑戦する姿勢とか哲学とか持ってない人が多いなと思っちゃって。DJやってて同じ選曲しても、違うパーティーだと人の反応も違うじゃないですか。それって選曲よりも「どういうパーティーだったのか?」とか「要はパーティーの質なんだろうな」というところに行きついたっていうか。そういう意味でもひとつ思想とか哲学を持ってやっていきたいと思ってます。今回のミックスがその答えだったり、表現方法だったりするんで。そんな中で選んだ曲なんです。 大きく2つに分かれて構成されてます。けっこう単純なんですけど。流れはトラックものとコード感があるものって感じで、トラックでハメて最後はまたコード感があるものに戻すというのを繰り返してるんですよ。最初のCevin FisherからVoicesまでと、Teki LatexからLoop7までの2つです。その中でトラックものとコード感があるものを繰り返してるんです。誰か気付かないかなと思ってたんですけど(笑)
この流れは自分のDJでもこういうことなんだなと思うんです。僕トラックものが好きなんだと自分で思ってるんですけど、結局どこかでコードものでつじつま合わせてるんですよ。メロディアスな感じをどこかに。たぶんそれって、メタルの人のバラード入れちゃう感じに近いのかな。メタルのアルバムでなんでバラードが入ってるのか、みたいなテンションわかりますよ(笑)。どこかで起承転結の結を作りたいんですよね。
流れは、もっと具体的にいえば、ツカミを作ってトラックものでハメる。そしてコードもので締めるって流れで、前半から後半でまったく同じく鏡みたいにその流れを作ってるんです。まさにいつもの僕のDJプレイそのもので、そのままパッケージにした感じです。だから「ド頭から最後まで大音量で聴け!」って。PCとかじゃなくて、アンプ通してね。やっぱりクラブで聴く音楽はベースが鳴ってないと!
 メッセージというか、YOSHITOSHI「Eddie Amador」とTeki Latexですよね。Teki LatexはこのEddie Amadorのオマージュ曲じゃないですか。だからタイトルも「Answers」で。最初は古い曲で、後半が新しい曲で、その後半は"Answers"からスタートして構成を区切ってるんで、あの「Answers」は僕なりの過去の曲に対するアンサーなんですよね。
まぁ、そんな深いものはないんですけどね。でもさっきも言ったように、やっぱり自分に対する挑戦であり、超えなきゃらならないものに対して。それはDEXPISTOLSだったりとか。そんなメッセージですかね。でもパーティー来てもらわないと伝わらないところもあるんですけど。時代に左右されない普遍的なものであることですかね。でもこのミックスって僕にしかやれないと思うんですよ。それをやりたかったし。
Eccyくんと、KAN TAKAHIKOくんの。入れた理由はカッコよかったし、自分でも現場でかけてるし、サポートもしたいんで。それと自分の新曲も入ってます。
ですね。シカゴアシッドの今版みたいな。アシッドベースハウスってイメージです。ミックスの中では一応ここがヤマです!自分の曲ですしね(笑)
そうですね、ニードルドロップ音はアナログから録って、頭にわざと置きました。それだけだと味気ないなと思って、録ったあとまだレコードが回っていたんで、そのノイズを録って配置したんですよ。針を擦ってる音って、位相のズレかわからないんですけど、それが気持ちいいっていう感覚なんですよ。2曲目の「HOT MUSIC」のところでそれを切ってるんですけど、突然レンジが狭まってる感じがするんです。ノイズで補われてるレンジの広さってあるんですよ。
そういうのは自分でも出したいというのはあって、でも単なる回顧主義に陥りたくないんで、最近の要素も入れたいし、それは選曲も、技術的なところも含めて。あとは座りながら作ってるといろいろガチャガチャやりたくなるんですよ。
そうそう、わりかしガチャガチャやってるミックスとか、一周とかですぐ飽きちゃうんですよね。ずーっと聴けるものって結構ベーシックでありクラシックなんですよ。
パッと聴き、「おっ!」ってなるようなものって、次飽きるんですよ。「これで大丈夫?」っていうものって次も聴くんですよ。ミックスじゃなくて、曲もそうで。「えっ?!これで大丈夫?」ってものは結構、僕的に好きなものの王道なんですよね。こんなザックリしてていいのみたいな。「俺でもできるんじゃない?」って思わせる感覚のものは人が引き込まれるって。あまりに完璧過ぎるものは、人は拒絶する傾向にあるのかなとか思ってます。
ひとりでやるときは、アナログでやることもありますよ。
James Blakeのアナログも買ったし、テクノとかの新譜も買ってるし、あと中古屋で古いの掘ったりとか。
いつもはCDかUSBなんですけど、やっぱアナログ全然違いますよ。わかってたことですけど。まず出音が違いますね。膝から下の音が出る感じ。CDだと腰までは出るんですけど、その下が出ない。とくに今ってスピーカーとか機材がよくなってきてるから、100%スピーカーのスペックを使ってないんですよね。デジタルでかけてる限りは。
メッセージというか、YOSHITOSHI「Eddie Amador」とTeki Latexですよね。Teki LatexはこのEddie Amadorのオマージュ曲じゃないですか。だからタイトルも「Answers」で。最初は古い曲で、後半が新しい曲で、その後半は"Answers"からスタートして構成を区切ってるんで、あの「Answers」は僕なりの過去の曲に対するアンサーなんですよね。
まぁ、そんな深いものはないんですけどね。でもさっきも言ったように、やっぱり自分に対する挑戦であり、超えなきゃらならないものに対して。それはDEXPISTOLSだったりとか。そんなメッセージですかね。でもパーティー来てもらわないと伝わらないところもあるんですけど。時代に左右されない普遍的なものであることですかね。でもこのミックスって僕にしかやれないと思うんですよ。それをやりたかったし。
Eccyくんと、KAN TAKAHIKOくんの。入れた理由はカッコよかったし、自分でも現場でかけてるし、サポートもしたいんで。それと自分の新曲も入ってます。
ですね。シカゴアシッドの今版みたいな。アシッドベースハウスってイメージです。ミックスの中では一応ここがヤマです!自分の曲ですしね(笑)
そうですね、ニードルドロップ音はアナログから録って、頭にわざと置きました。それだけだと味気ないなと思って、録ったあとまだレコードが回っていたんで、そのノイズを録って配置したんですよ。針を擦ってる音って、位相のズレかわからないんですけど、それが気持ちいいっていう感覚なんですよ。2曲目の「HOT MUSIC」のところでそれを切ってるんですけど、突然レンジが狭まってる感じがするんです。ノイズで補われてるレンジの広さってあるんですよ。
そういうのは自分でも出したいというのはあって、でも単なる回顧主義に陥りたくないんで、最近の要素も入れたいし、それは選曲も、技術的なところも含めて。あとは座りながら作ってるといろいろガチャガチャやりたくなるんですよ。
そうそう、わりかしガチャガチャやってるミックスとか、一周とかですぐ飽きちゃうんですよね。ずーっと聴けるものって結構ベーシックでありクラシックなんですよ。
パッと聴き、「おっ!」ってなるようなものって、次飽きるんですよ。「これで大丈夫?」っていうものって次も聴くんですよ。ミックスじゃなくて、曲もそうで。「えっ?!これで大丈夫?」ってものは結構、僕的に好きなものの王道なんですよね。こんなザックリしてていいのみたいな。「俺でもできるんじゃない?」って思わせる感覚のものは人が引き込まれるって。あまりに完璧過ぎるものは、人は拒絶する傾向にあるのかなとか思ってます。
ひとりでやるときは、アナログでやることもありますよ。
James Blakeのアナログも買ったし、テクノとかの新譜も買ってるし、あと中古屋で古いの掘ったりとか。
いつもはCDかUSBなんですけど、やっぱアナログ全然違いますよ。わかってたことですけど。まず出音が違いますね。膝から下の音が出る感じ。CDだと腰までは出るんですけど、その下が出ない。とくに今ってスピーカーとか機材がよくなってきてるから、100%スピーカーのスペックを使ってないんですよね。デジタルでかけてる限りは。いや、なんか体感的なんですけど、膝から下の音が出るとホント踊り続けられるんですよね。思ったんですけど、芝浦"GOLD"に初めて行ったときの感覚ってそんな感じで。初めてだから衝撃的で頭ン中で過大評価してるのかなと思ったんですけど、最近アナログでプレイした瞬間に「あーこういうことか!」って思って。別に過去のことを美化してるわけじゃなくて、実際出てなかったんですよ。アナログでやることによって出るようになったのと、あとDJやってる感じがいいんですよ。すぐ針飛ぶし、すごく集中するし、探すのめんどくさいし。でも不便なところがいいのかな。やっぱり人間って不便になるとそこを補充するように、いろいろなアイデアでそこを埋めようとするんです。便利になってくると進化じゃなくて、退化するんじゃないですか。不便さを人間持った方が研ぎ澄まされるのかなと思うし。 そうそう。僕らがやらなきゃいけないことって、いいものをいいって選ぶ力であって、要はそこを研ぎ澄まさないきゃいけないわけで。そうするには自分の内面を磨いたり鍛えなきゃいけないというのはあるんじゃないですか。いいか悪いかわからなくってきて、それを何で埋め出してるかっていうと、それは情報で埋めてるんですよ。「このシーンで流行ってて、こういう人が作ってるからカッコイイんです」とかね。そういう先入観。じゃ、まったくその情報を知らない人たちに、フロアで投げたときにどうなんだ?ってところなんです。 それは、さっきも触れたけど、ニューヨークのクラブ黄金期ってやっぱり平日が盛り上がってたと思うんですよね。なんでかっていうとニューヨークのクラブは週末は観光客みたいなのが多いから、マンハッタンに住んでるやつらは、週末クラブなんて行かないで家でゆっくり過ごすって聞いたんです。それオシャレだなーって(笑)。平日サクッと遊んで、家近いから帰るみたいな。それに習って平日カッコイイパーティーができたらなと。 「HOUSE CLAPPERZ VOL.1」のリリパは7月21日にあります。リリパに関しては人数制限なしなんで、みなさん来て下さい! いや、今のところは制限解除は考えてないです。でも先着30名様は一般でも入れるんで。 うちのクルーのJOMMYがついにデビューってことで、年末くらいにリリースしたいと思ってます。あとは別シリーズになるか、まだわからないんですけど、PUNKADELIXが続きます!