Interview : Yasuo Takata
Photo :Kojun Shimoyama
Editor: Atsuki Iino
Powered by Sound Of Vast
Photo :Kojun Shimoyama
Editor: Atsuki Iino
Powered by Sound Of Vast

6月28日(月)、DJ Sodeyamaの別名義The People In Fogによる8年ぶりのアルバム『1977』が、アムステルダム発日本人レーベル「Sound Of Vast」よりリリースされた。『1977』のタイトルは、多大な影響力を持つシカゴのハウスの聖地「Warehouse」が誕生した年を意味し、作品を通じて様々なスタイルのハウスミュージックを表現している。また、アルバムのリリースとは別で、リミックスEPの制作も決定。アルバムのリリースに際して、DJ Sodeyamaとリミキサーとして参加するSatoshi Tomiie、Chidaに今回リリースされる楽曲の制作背景や、それぞれが歩んできたキャリアなどについて語ってもらった。
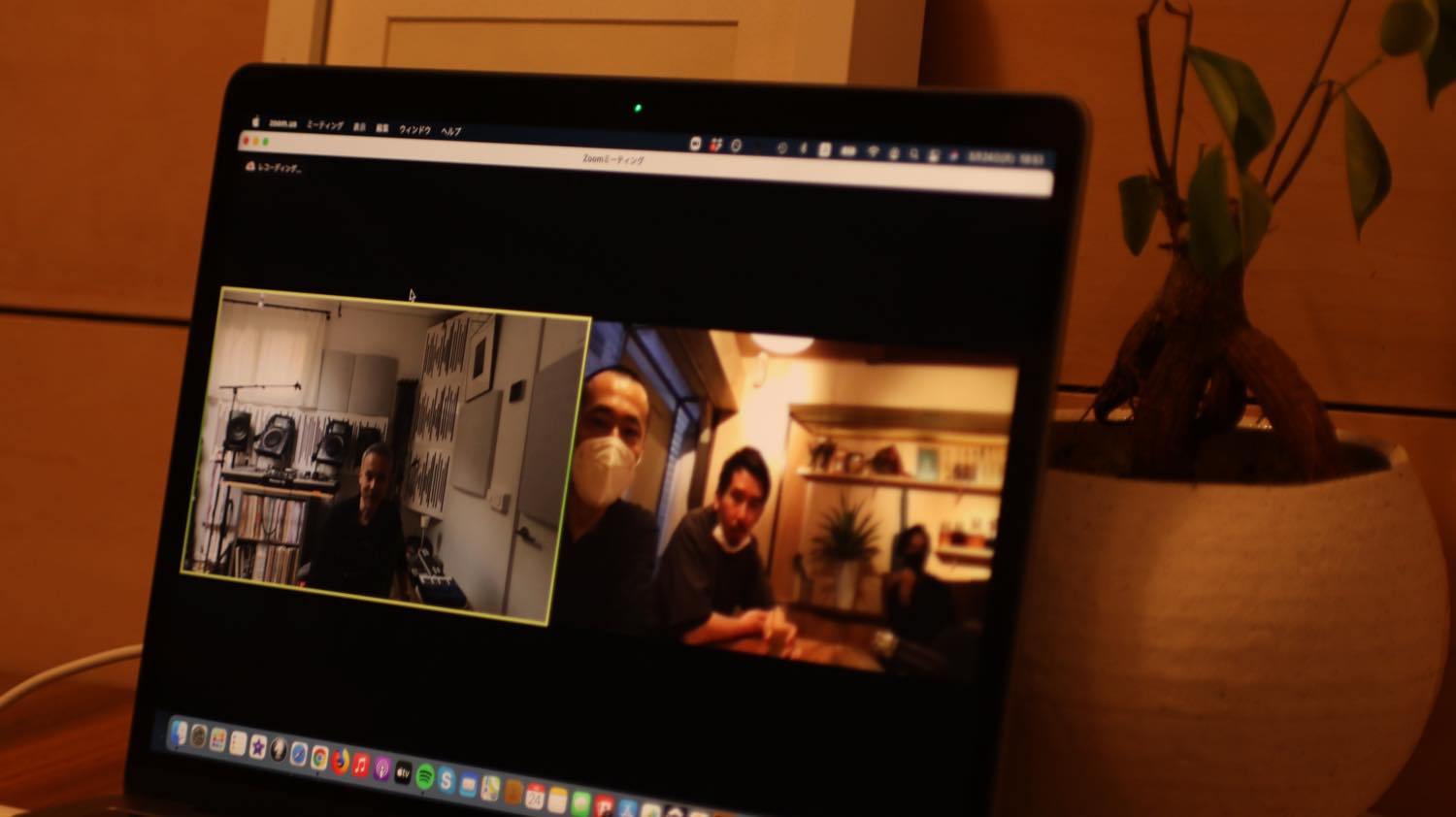
――まずはそれぞれのDJを始めたきっかけや時期などから教えてください。
Sodeyama:僕が始めたのは93、4年あたりです。きっかけは※GOLDとかのクラブに若い時から遊びに行ったりしたので。中学生の頃からよく知らずに『The Whistle Song』とかも聴いていました。
※1989年から1995年にかけて、東京都港区芝浦で営業していた伝説的クラブ
Satoshi Tomiie:中学生・・・すごいね(笑)中学生でハウスを聴くのは変わってるんじゃないですか?(笑)
Sodeyama:Crystal Waters『Gypsy Woman』が中3の時にリリースされて、そういうのを聴いてました。高校入ってクラブに行くようになりました。ちょうどダンス甲子園とかが中学生の時に流行ってたのもあって、周りがダンスやってる子とかが多かった時代だから、「ちょっとクラブ行ってみようぜ!」みたいな感じで。
――Chidaさんはどうですか?
Chida:ほとんどSodeyamaくんと被りますね。高校の時にまさしくダンス甲子園ブームで、僕もダンスをしてて、クラブミュージックを聴き始めた感じですね。僕仙台出身で仙台のクラブとかディスコに行ってたんですけど、そこでかかる曲とかで自分が踊る用にミックスを作ってたんですよね。
Sodeyama:Chidaさんダンサーだったんですか?そこが驚きですよ(笑)
Chida:地元の周りの友人も皆んな踊ってたんで自分も(笑)高校生なんでバイト代でレコード買うのが精一杯で機材は持ってませんでした。ある時ディスコでDJやってる先輩が「夜仕事の間機材自由に使って良いよ!」と部屋の鍵を貸してくれたんですよ。新譜の12”を買うたび、機材部屋に通ってはミックステープ作りにハマっていって。高校卒業後すぐに東京に出てきたんですけど、とにかくGOLDやYELLOWに行きたい一心で(笑)東京では誰もDJの知り合いは居ないし、当時ってDJになりたいと思ったら「とにかくミックステープをDJに渡せ!」みたいな感じだったんで、いろんなDJにミックスを渡してたんですよ。
Satoshi Tomiie:誰に渡してたんですか?
Chida:EMMAさんやDJ NORIさん、川内太郎さん他、ハウスDJの方に片っ端から渡してました。
Satoshi Tomiie:なるほど。
Chida:その甲斐あって、渋谷のCAVEで93年あたりからDJをやらせてもらう事になるんですが、その頃にはダンスの事より新譜のレコードとDJの事ばかり考えるようになってました。
Satoshi Tomiie:その頃からハウスなんですか?
Chida:そうですね。高3の時にFrankie Knucklesの『Beyond The Mix』(特に『The Whitsle Song』と『Rain Falls』)に出会った時の衝撃が大きくて。TomiieさんもメンバーだったDef Mixに夢中でした。
Satoshi Tomiie:なるほど。じゃあずっとハウスな感じですか?
Chida:そうですね。90年代はとにかく毎週のようにGOLDやYELLOWのハウスのパーティーに通っていましたね。DJのスタイルも。
.jpg)
――Tomiieさんの始まりはどれくらいの時期でしたか?ニューヨークに移った経緯だったりとか色々教えていただきたいです。
Satoshi Tomiie:元々DJの前はピアノをやってました。クラシックの楽譜を読むのが嫌だったので、ジャズをやってたんですよ。友達の影響でクラブミュージック的なところに興味はあったんですが、その頃はハウス自体まだ存在してなかったですね。
――なるほど。
Satoshi Tomiie:その頃のクラブミュージックといえばヒップホップだったので、まず最初はヒップホップから入りました。
Sodeyama:それって日本にいる時ですか?
Satoshi Tomiie:はい。いわゆるモダンジャズみたいなものを高校生の時にやってましたが、それこそHerbie Hancockの『Rock It』とかそういう感じの時代だったので。その後ヒップホップにはまっていって、初期デフジャムのドラムに影響されて、カセットMTRでトラックとか作ったりしてましたね。ドラムマシンを買って、ビートを作ってタンテでスクラッチしたりピアノを上に弾いて録音してみたいな。でも結局ヒップホップってカルチャーじゃないですか。その当時だとブロンクスの若者がやってるような感じだったので、そこに自分が入っていくのは違うなと思って。
――なるほど。
Satoshi Tomiie:色々やったりしてるうちに友達が持ってたシカゴのミックステープでハウスミックスを初めて聴いて、面白いなって思いましたね。もう少し掘っていったら、ハウスミュージックはカルチャーはカルチャーだけど、匿名性が高いというか、ラッパーという主役なしに楽器が作り出すグルーブだけで成立するというか。ヒップホップとの違いを感じました。
――そうだったんですね。
Satoshi Tomiie:それで88年くらいにFrankie Knucklesと中村直さんの日本ツアーがあって。それが多分ハウスDJ初来日ですね。友達がそのツアーを仕切ってた広告代理店でバイトをしていて、オリジナル音楽を作るみたいな話になって、なぜか僕に話がきたんです。それで作った曲をFrankieが聴いてくれて、社交辞令で「かっこいいね、今度一緒にやろうね。」みたいに言ってくれて。僕大学生だったので、「マジですか?」みたいな感じで舞い上がってしまい、その後ひたすら家で曲を作ってました。
――すごいですね。
Satoshi Tomiie:DJに関しては、その頃西麻布にTOLOSってお店があって、木村コウくんと高木康行くんが2人で水曜日にDJしてて。そこに通うようになって、彼らと知り合いになって、みたいなところからハウスのDJを始めました。大学生の時ですね。おかげで大学5年いましたけど(笑)
全員:(笑)

Satoshi Tomiie:DJと曲制作は同時に始めましたね。その頃、東京とニューヨークを行き来するようになって、生意気にもGOLDでもDJをやらせてもらえるようになりました(笑)始めたばっかりのくせに。
全員:(笑)
Sodeyama:90年くらいですか?
Satoshi Tomiie:そうですね。GOLDが平日でもパンパンだった時です。
Sodeyama:それって『Tears』リリースしてからの話ですよね?
Satoshi Tomiie:そうですね。『Tears』は作ったのが88年とか?この辺の話は長いのでまたの機会にしましょう(笑)
全員:(笑)
――ありがとうございます。今度はSodeyamaさんに聞きたいのですが、Sodeyamaさんはハウスからテクノに徐々に変わっていったような気がします。90年後半になって、ダンスミュージックにおいて色んなジャンルが出てきたことも理由としてあるかと思いますが、どういった感じで傾倒していったか教えていただけますか。
Sodeyama:98年くらいのまでのDef MixしかりRoger Sanchezとか、ハウス勢の活動が凄かったですよね。
Chida:90年代ってMariah CareyとかMichael Jacksonとかビルボードのアメリカで流行ってたのをかなりの数Def Mixがリミックスやってましたよね。R&Bシンガーのハウスバージョンを。
Sodeyama:Mariah Careyのリミックスをやるとか想像を絶する話ですよね。 2000年以降、90年代初期ほどのインパクトのものが個人的には少なくなっている感じがして、ハウスばっかり聴いてましたが、他のジャンルを聴くようになりました。
――なるほど。
Sodeyama:その時にOliver Hoとかのテクノを聴き始めて。パーカッシブな派手すぎないミニマルというか。意外とピッチ下げればJoe Claussellと混ざるなみたいな。そこからちょっとずつテクノになっていった感じですね。
――なるほど。Chidaさんはどうですか?
Chida:ダンスミュージックレコードでDan Kっていうプロデューサーの方が働いていたのですが、彼が勧める音がニューヨークハウス以外で面白い音がいっぱいあって。Idjut BoysとかDJ Harvey周辺のディスコリコンストラクト、エディットモノですね。2000年頃からは北欧のニューディスコ、西海岸からはプログレッシブでもサイケデリックな要素のハウスの音も入ってきて。その時代ごとの新しい波を純粋に受け止め続けてきた感じですかね(笑)
全員:(笑)
Chida:Idjut Boysが青山LOOPに来日した時に遊びに行ったんですが、その時にぶっ飛ばされて。「なんだこれは!」って。ニューヨークハウスの呪縛から離れられた瞬間でした(笑)
Sodeyama:あの呪縛は離れられないですよね。
Chida:しばらく。99年くらいまでは(笑)
Satoshi Tomiie:ちなみにニューヨークハウスっていうのはどのへんの話ですか?
Chida:Def Mix、Masters At Work、Strictly Rhythmとかですかね。あとはTrax、Cajual、Reliefとかのシカゴハウスもずっと追っかけてたましたね。
Satoshi Tomiie:じゃあニューヨークのDJがかけてる感じですね。
Chida:はい、まさしく。
――Tomiieさんは95年あたりから色々変わってきたと思うんですけど、その辺のお話を聞かせてください。
Satoshi Tomiie:90年代は、特にメジャーレーベル仕事などはホームスタジオで全部作り上げる方法では難しかったのでスタジオでエンジニアを雇い、ミュージシャンを雇い、機材をレンタルし、みたいな今とは違う制作方法が普通でした。
Sodeyama:凄かったですよね。
Satoshi Tomiie:スタジオではリミックスなど48時間で一曲全部やらなきゃいけないっていう事情である意味工場みたいな感じでしたね。1日に50万ぐらいの経費がかかるので、1日もレコーディングを伸ばせないんですよ。そういう裏事情があって、自分の曲を少しやりつつ、たまにFrankieを手伝ってみたいな。音楽的には90年くらいからそのスタイルを中心にやってるから、5年くらいやって、「次に行くにはどうしよう?」ってなりましたね。なんだかんだ言ってDef MixはMorales、Frankieが看板なので、僕が「こうした方が面白いかな?」と思っても、中々難しくて。Def Mixサウンドみたいなものは、言ってみたらフォーマットだから。ピアノがあって、歌が中心で、それに合わせてうまい具合にトラックを作っていく感じ。
全員:なるほど。
Satoshi Tomiie:レコードに関して言うと、初めの頃(80年代の終わり)はChidaくんが言ってたようなニューヨークのDJがかけてたシカゴっぽい曲をいっぱい買ってましたた。US国内盤はニューヨークのレコード屋なら割と普通にどこでも売ってて玉数が多かったので、すぐ売り切れてしまうようなヨーロッパからのインポートを求めてレコード屋さんにマメに通ってました。ニューヨークのレコードはみんな持ってて当たり前みたいな感じでしたし、枚数の少ない輸入版の取り合いみたいになっていたので。そうしているうちにいろんなレコードを聴かせてもらって新しい音楽を知っていきました。いっぱい回って、新しいものを仕入れてっていう繰り返しでしたね。レコード盤しかない時代だったし。
――なるほど。
Satoshi Tomiie:他の音楽を色々聴いているうちに「もう少しエレクトロニックな方向に行ったら面白いかな?」って思って。98年くらいに作ってたアルバムかな?きっかけになったのは。
Sodeyama:『Full Lick』ですかね?
Satoshi Tomiie:そうそう。僕が好きないわゆる「ソウルミュージックベースのグルーヴ」とはちょっと違ったり、全く違う方法で歌を処理していたり、これは面白いな、と思いましたね。そのあたりからイギリスのプロデューサーが作ってるような音を聴き始めましたね。
――ありがとうございます。それではその後の2000年から2010年あたりの活動はどうでしょうか?ここら辺からみなさんの動きに色々変化があったかと思います。
Sodeyama:ジャンルのことではないのですが、2000年から2010年って、ダンスミュージックカルチャーというよりもパーティーカルチャーにみんな力を注いでた気がします。自分も含めて。
Satoshi Tomiie:どういうことですか?
Sodeyama:自分もそうでしたが、日本人のDJって曲作ってない人が多かった。レーベルも2000年頃って、少なかったと思います。日本のインディペンデントのダンスミュージックレーベルって。
Chida:Flower Records、Crue-L Records、Nitelist Music、Sublimeとか?
Sodeyama:そうですね。それも先輩方がやってるレーベルが全てで、同世代でレーベルもやってて音楽作ってリリースもしている人って少なかったんです。
――そうですね。
Sodeyama:パーティーをやって、外タレ呼んで、人をいっぱい入れる事に必死になっていて、いつの間にかアーティストや音楽家っていうよりも、DJ兼オーガナイザーみたいな感覚でパーティーをやることにすごい力を注いでいた。その頃、僕もトラック制作ってほぼやってなかったんですよ、ちょろっとはやってたんですけど、あんまりそこに面白みを感じれないままやっていて。やっぱりDJとパーティーやってるのが楽しいみたいな。
.jpg)
Satoshi Tomiie:なるほど。言ってることは分かるけど、世界中どこも同じような感じじゃないのかな?
Sodeyama:僕の感覚だと海外の人はみんな曲作ってるイメージがあります。
Satoshi Tomiie:それは確かにそうですね。ブランディングもオリジナルの曲があってからのアーティストがいてって感じですね。
Sodeyama:音楽を作る事が当たり前というか。
Satoshi Tomiie:確かにその時はこの人はDJ、この人はプロデューサー、みたいな分け方はもうなかったもんね。それこそ昔はShep Pettibone(シェップ・ペティーボーン)がマドンナのプロデュースをして儲ったからDJを引退したみたいなことがあったけど。
全員:(笑)
Satoshi Tomiie:その当時はDJは食えないけど、プロデューサーになったら食えるみたいな。そういう時代と今は逆だからね。
Sodeyama:勿論DJをして人を楽しませる事は大事だし、パーティーも大事。でも、音楽を作ってリリースするとかレーベルやるとかも同軸で当たり前にあるっていう感覚がほぼないまま「クラブでイェーイ!」って遊んじゃってたんで。
全員:(笑)
(1).jpg)
Sodeyama:でもパーティーだけでも、楽しいじゃないですか。そのノリで、日本のクラブもめっちゃ人が入ってたので。
Satoshi Tomiie:入ってましたね。
Sodeyama:「あ、なんだ、日本のクラブシーン凄い!」みたいな(笑)そんな感覚だったのが2005年くらいまでで。そこから少しずつ「あれ?ちょっと違うかもな。」と感じ始めて、やっと機材を買い始めるんですけど、元々楽器もできないし楽譜も読めないんで、最初チンプンカンプンで。なんとか必死にやって、徐々に何とかリリース出来る様になった感じです。どのパーティーも、毎週1,000人とか普通に入っていたので、どこか安心してしまって、アーティストの育成とか、曲を作るとかレーベルやるとかクリエイティブな部分がシーン全体的に出来ていなかった。 ベルリンとかみたいに、色んなDJ達がスタジオを持って「みんなでシェアしようぜ!」みたいな事って都内ってなかなかできないじゃないですか。だから、どうしても仲良くなったDJと「今度スタジオきて一緒に曲作ろうぜ!」ではなくて、「今度パーティーやろうぜ!」ってなっちゃうんですよね。
Satoshi Tomiie:周りがそういう雰囲気じゃないとね。それこそベルリンは家賃が安くて周りの人がそうだからだけど。
Sodeyama:そう。難しいですよね。2010年くらいにやっと「レーベルやってみようぜ!」とか「もうちょっと音楽制作頑張ってみようぜ!」みたいな動きがなんとなく周りで出てきた感じですね。
Satoshi Tomiie:作る人が興味なくて、サポートする側もあんまり興味なくて、お金ももう回っちゃってると、それこそ日本の携帯電話みたいに中で回ってしまうからいいじゃんみたいな感じになっちゃいますよね。
Sodeyama:結果、自分達DJもお店も、人が入ってるから、音楽を発信するという部分よりパーティーをフォーカスし過ぎてしまって・・・
Satoshi Tomiie:海外に行ったりするにはそういうのをバランスよくやるべきなんだけど、うまくいってるから必要を感じなかったんでしょ。
Sodeyama: そうなんですよね。

――Chidaさんは2000年から2010年あたりの時はどうでしたでしょうか。
Chida:93年からレコード会社でダンスミュージックのプロモーター、2000年からはマネージメント事務所でアーティストのマネージメントA&Rという仕事をしながらアナログレーベルを運営してました。4枚しかリリース出来なかったんですが、2002年からはまたレコードレーベルでの仕事を始めて。
――なるほど。
Chida:裏方の仕事が好きだし自分に向いていたってのもありましたね。かれこれ15年くらいの間、昼間は裏方の仕事に専念しながら、夜は自分でオーガナイズするパーティーや、Idjut BoysやPrins Thomasなど外タレがelevenやYellowでプレイする際に共演させてもらってました。DJを始めて20年経ってやっと自分に少し自信もつき始めたのもあり、2009年の春に独立して、自分でレーベルEneを始めました。Abletonを触り始めたのは2006年頃で、初めは自宅にあるディスコのレコードを片っ端から自分のDJの現場用にエディットしまくってました。100曲位エディット作ったところで曲のアレンジや音の構成が判ってきて、オリジナルトラックを作り始めていたのですが、2010年にIs It Barealic?のCoyoteが来日して一緒にDJした際、「リミックスしてくれないか?」といきなり言われたんです。当時は僕自身の作品はまだどこからもリリースしていなかったんですが、Eneからリリースすれば自分で尻拭いできるし、トライしました。そこそこの手応えがあったので、それをきっかけに本格的に毎日制作に時間を費やすようになりました。
Sodeyama:2000年から2010年は色んな事を感じて、深く考える10年でしたね。
――結構2人の方向性はハッキリ変わりましたね。
Chida:自分達でパーティーもDJも続けてましたが、東京のクラブでは毎週ゲストDJが海外から来る中、ローカルのDJはどうしてもウォーミングアップやクロージングを務める事が多いじゃないですか。それで自分たちが次のステップ・・・「海外のクラブやフェスにブッキングされるようになるにはどうしたらいいのだろう?」って考えた時、とにかく自分の名刺になるような曲をリリースしないといけないなと思って。
――自然な流れですね。Tomiieさんは2000年から2010年、レコードではなくPCだけでやってたりとか、いち早くデジタルでDJしてたようなイメージがあったんですが、その辺の経緯を教えていただけますでしょうか。
Satoshi Tomiie:皆さんご存知のように、80年90年代いっぱいはレコードがないとDJできなかったじゃないですか。CDJが出てきたけど、CDJごと持っていかないとできなかったし。実際CDJ-1000が出た時は、自分でクラブに持っていってたりしてました。
――すごい(笑)
Satoshi Tomiie:レコード会社もディストリビューターもイケイケだったのですが、段々と売り上げが落ちていっちゃって。CDJが出てきたのと、自分でCDを焼いてかけられるっていう点は強かったですね。旅が多くて、レコードだと「あ、飛行機着いたのにレコード着いてない・・・」みたいなことがよくあったので。しょうがないからレコードの半分は機内持ち込みで残りの半分は預けてリスク分散をやってたんだけど、「CDJで全部できるならCDになったほうがよくないか?」みたいに思って。送られてくるプロモもレコードだったんで、結構な量でそれを聴くのも大変で。ちょっと旅行に出てしまうと溜まってもう聴けないみたいな。しょうがないからレコードプレーヤーごとスーツケースに入れて、持ち歩いてました。旅先のホテルで聴いてましたね。
全員:(笑)

Satoshi Tomiie:こんなの大変じゃんって(笑)だんだん送られてくるプロモもレコードが売れなくなってきたから、CDになってきて。レコードは高いしどんどん売れなくなっていって、レコード店もガンガン潰れていっちゃって。そういう状況になって「レコードキツくないか?」みたいな話になって。あとDubfireに「サトシ、Seratoがすごいよ!」って勧められて。始めはDJ中に止まったらやだなと思って警戒してたんだけど、まあやってみたら便利だなって。こんなに便利だったら突き詰めるところまでいってみようってなって、SeratoとPC、CDJコントローラーででやってました。その後はTRAKTORになったんだけど、TRAKTORって4曲繋げるじゃないですか。
――そうですね。
Satoshi Tomiie:テクノDJだったら色んなことができるけど、ハウスだとただビートを合わせて繋ぐだけだから、すごいつまんなくて。
全員:(笑)
Satoshi Tomiie:それで最終的にレコードに戻ったみたいな。曲繋ぐ間は何かやってたいですね。
.jpg)
――なるほど。次は楽曲制作についてお三方に聞きたいです。作り方や音楽のスタイルも含めて今も昔と変わらないところってありますか?
Sodeyama:ずっと変わってる感じです。特にここ2、3年もう日々やり方が変わってます。ハードウェアメインだったりプラグインメインだったり・・・。やっと音楽の作り方をこの2週間くらいで知った気がします。
全員:(笑)
Sodeyama:それくらい僕はずっと勉強をしている身です。
――じゃあずっと変わっているってことですね。
Satoshi Tomiie:Sodeyamaくんは全部コンピューターですか?
Sodeyama:ハードと半々くらいですね。ドラムマシンも使うんですけど、MIDIがめんどくさくてすぐオーディオにしちゃいます。
Satoshi Tomiie:分かります。
Sodeyama:ドラムマシンも打ち込むのがめんどくさいから、とりあえずキック1個録ってシーケンスに並べるみたいな。それで例えばTR8だったら、とりあえず録ってすぐ加工しまくるみたいな。加工してるのが楽しいみたいなとこがあるので。Elektronのドラムマシンとかシンセも色々持ってましたが、保存の仕方すらも分からないまま売りました。難しすぎて。
Satoshi Tomiie:あれは合宿しないとだよね。
Chida:あれはあれだけで一回突き詰めないと。
Sodeyama:モジュラーシンセみたいな使い方になってました・・・。保存分からないし、電源切って立ち上げてまたやってみたいな。大体うちにある機材はどれも保存の仕方が分からないまま使ってます。一瞬モジュラーも始めましたが、僕には向いてなかったですね。
Satoshi Tomiie:あぁ・・・
Sodeyama:ワンラックくらい揃えてもう今は眠ってます。蓋を開けないことにしました。
Satoshi Tomiie:まああれは沼だから。
全員:沼(笑)
Satoshi Tomiie:僕は沼にどっぷりハマりまくってしまって。でも沼のサイズを決めて、沼の大きさを広くしない方向で欲しいものあったら売ってます。
Sodeyama:結構入れ替えてるんですか?
Satoshi Tomiie:入れ替えてますね。これ買いたいからこれ売ろうみたいな感じで。

――なるほど。Tomiieさんはお話されたように、モジュラーシンセを最近多用されてるかと思いますが、現在の制作のやり方で昔から変わってないところってあったりしますか?
Satoshi Tomiie:なんだろうな。元々始めた頃は80年代くらいだからね。
――そうですよね。
Satoshi Tomiie:簡単に言ってしまえば元に戻った感じで、当時との違いは今はDAWだから録音が簡単。
全員:なるほど。
Satoshi Tomiie:ここに戻ってくるまでに色々なやり方に手を出しましたね。2000年くらいかな?コンピューターにプラグインを入れてやれば旅先で作れるので「他に機材全部いらないな。機材売っちゃえ!」みたいな感じで半分くらい売っちゃったんです。今となっては売らなきゃよかった機材がいっぱいあります。それで旅先でコンピューターでやってみたんだけど、やれやしなかったですね。全然インスピレーションが湧かないのと、音を作るというよりプリセットを選ぶ大会みたいになっちゃって。プリセットの気に入らない部分を直そうかなと思ってもマウスでいじるのはあまり直感的でなかったり。結局今は完全にハードウェアに戻ってしまいました。ハードウェアに戻っていいなって思うところはやはり直感的な演奏ができるところで、シーケンサーのスタートボタン押して、シーケンスや音色を同時にどんどんエディットしていって、エフェクトも色々いじりつつそのライブ演奏を録音して終了みたいな感じのスタイルができるので作業が早いんですよ。
――ジャムですね。
Satoshi Tomiie:そうですね。1曲でアレンジをあーでもないこーでもないってずっとやるのが嫌なので。一気に録ってしまって、終わりにしたい感じ。そうすると後で悩まないから。今はハードウェアで完結できるスタイルに戻ったのでソフトシンセとかは使わないですね。
――なるほど。ありがとうございます。Chidaさんはどうですか?
Chida:制作し始めた頃はドラムマシンやサンプラー、シンセなども持ってたんですが、使いこなせるようになる前にAbleton Liveに出会ってしまって。今はmacbookとKORGのTRITON Taktileのみです。ARP ODYSSEY, Polysix, MS-20, Monopoly, Wavestation他、ソフトシンセでも自分的には十分満足な音が鳴るので、多用してます。
Satoshi Tomiie:あれは音いいですよね。
Chida:今から全てのビンテージ機材を揃えようと思ったら難しいし、旅先でも作業する事が多かったので、ラップトップだけでも作業できるのは最高だなと。
Satoshi Tomiie:Abletonのソフトシンセみたいなところから入ってるんですね?
Chida:はい、初めはAbletonのソフトシンセだけ使ってました。
Satoshi Tomiie:だったら逆にそれでいいのかもしれないですね。僕は結局ハードウェアから入ってしまったので、そっちから入ったらコンピューターが使えないおじさんになってみたいな(笑)
全員:(笑)

――最後にSodeyamaさんの今回のアルバム『1977』の制作背景や秘話を教えてください。ここからはレーベルオーナーのKnockにも参加してもらいます。
Sodeyama:Sound Of VastからはEPとブート合わせると5枚くらい出してますが、4年くらい前から「そろそろアルバムやりましょうよ!」って言われてて。それでやっと2018年に作り始めて、「2019年ぐらいにはリリースしよう!」って言ってましたが、結局やってなくて。その後「2020年の春ぐらいには出せるようなスケジューリングでやりましょう!」って言ってたんだけど、間に合わなくて。
全員:(笑)
Sodeyama:出来上がってるものにしっくりも来てなくて。何曲か送ってたけど量も足りてなくて。そのまま2020年明けてしまい・・・ちょっとそろそろみたいなタイミングで丁度コロナの話も出てきて。その時に、これコロナでアルバムやらなくなりそうだな・・・っていうのを薄々気づきつつ、またやらないみたいな(笑)
全員:(笑)
Sodeyama:そしたら連絡きて、「一旦レーベルも止めるので白紙に戻します。」ってなって。しばらくして夏くらいに「このまま止めてても仕方がないので、アルバムやりませんか?」って言ってもらい、僕もだらだらしていてもしょうがないし、「よし!じゃあやろう!」って。もともと作ってた曲はほぼ捨てて、作り直しました。
Knock:そこからのスピードがすごかったですよ。
Sodeyama:試行錯誤が多かったです。普通のダンストラックを9曲10曲入れたレコードでは、このご時世には合わない面もあり、ネタものやテンポが遅いものなど、リスニングぽい曲も入れました。
――フューチャリングアーティストも含めてですね。
Sodeyama:そうですね。
――それをちゃんと完成させたんですね。
Sodeyama:締め切り過ぎてましたけど・・・。9曲中、締め切り過ぎて作ったのが半分。
――夏休みの宿題系(笑)
Sodeyama:ヤバい、締め切りだ!って日に全然できてなくて、自分から連絡するのやめようと思って。
Knock:僕は連絡するんですけど(笑)
Sodeyama:「やります!」って慌てて返答して(笑)
.jpg)
――今回リミックスEPが別で出るようですが、そちらに関してはいかがでしょうか。TomiieさんとChidaさんも参加されていますよね。
Sodeyama:なんか本当にすみませんっていう気持ちです(笑)90年代のDef MixにいるTomiieさんをリアルタイムで知っているので、恐れ多過ぎて・・・。「どうオファーしていいか分からないね・・・。」ってノックに相談をしてて。でも、今回のアルバム『1977』っていうタイトルもFrankieがレジデントを務めたシカゴのウェアハウスがオープンした年というところから引っ張ってるので、今回のアルバムのコンセプトを考えるとTomiieさんに何とかお願いしたかった。
Satoshi Tomiie:なるほど。でも当時の音とは関係ない音に出来上がってしまう気がしますけど。今でも「『Tears』っぽいのがいい!」とか言われることがあって。そういうのやってないんですよ(笑)
全員:(笑)
Satoshi Tomiie:逆に一周して当時のグルーブ感みたいなのを気に入って買うレコードもいっぱいありますけど。いわゆるその当時のDef Mixの音は楽しめないと思いますけど、お許しください(笑)
Sodeyama:そこを求めている訳ではなく、あくまでも今のTomiieさんの形とうまく混ざる感じになったらいいなっていう。
Knock:そうですね。がっつり原点回帰ってコンセプトではないので、あくまでも昔もあって今もあるって形のアルバムになってます。
Satoshi Tomiie:その当時の買ってもらってた繋がりでお願いされるのは光栄ですね。
Sodeyama:多分Satoshi Tomiieリミックスはほぼ持ってますよ。
全員:(笑)
Satoshi Tomiie:お恥ずかしい限りです(笑)
(1).jpg)
Sodeyama:当時90年代に僕が高校生でTomiieさんの曲を買ってた時に、20年後、25年後にリミックスを頼む日が来るなんて考えてもなかったので、すごく嬉しいです。
Satoshi Tomiie:25年経ってまだやっててよかったです。
Chida:僕もTomiieさんの音に最初に触れたのが1991年なので、30年ですよ。感慨深いですね。
Knock:現在進行形のTomiieさんのリミックス楽しみです。
Satoshi Tomiie:頑張ります。
――Chidaさんはこのアルバムのリミックスに参加していかがでしょうか?
Chida:僕は元々ミュージシャンではないのもあって、オリジナル曲の制作よりも、リデリットやリミックスの作業が好きなんです。今回リミックスのお話頂いてから、自分がガラッと雰囲気変えられそうな曲はどれかなってずっと聴き込んでて。
――それぞれがリミックスする曲を選んだ感じなんですね。
Chida:はい。Tomiieさんが『Less Is More』、あとLicaxxxさんは『Down The Drain』を選んだと聞きました。で、残りの曲を聴き込む中で、デビュー前からMonkey Timersの2人は知っていたし『Come To Me feat. Monkey Timers』がBPM110くらいの遅めのアシッドディスコハウスだったので、BPMをぐいっと上げて、かつガラッと雰囲気変えられるかな?と思い、『Come To Me feat. Monkey Timers』を選びました。
Sodeyama:Knockにも言ってないけど、『Come To Me』って曲のタイトルはTomiieさんの『Come To Me』からきてます。
全員:(笑)
Satoshi Tomiie:なるほど、仕込みだ!
Sodeyama:一応いろんなところの絡みは作ろうって思いまして。
Knock:結構僕の周りは今回のリミックスに関して「意外な組み合わせだね!」って言ってるんですが、話をこうして聞いてくとルーツが皆んなほぼ一緒なんですよね。
――最後に何か一言ありましたら。
Knock:リミックスの完成を楽しみにしています!
Satoshi Tomiie、Chida:頑張ります!
――皆様ありがとうございました。
.jpg)
Photo by Yoshimasa Matsunaga
Release InfoThe People In Fog 『1977』
Release Date: 2021.6.28(Mon.)
Label: Sound Of Vast
Format: 2LP (見開き仕様) / Digital
Tracklist:
1. South Jefferson
2. Holy Spirit
3. No Boundaries
4. Less Is More
5. Come To Me feat. Monkey Timers
6. Mr. Dub
7. Wayback
8. Down The Drain feat. Sunga
9. New Period feat. Hiroyuki Kato
10. Platz feat. YOSA (Digital Only)
11. Burnt feat. S.O.N. (Digital Only)
リリースURL
https://linkk.la/1977s







